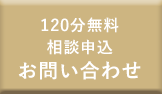お役立ちコラム
同友会の例会にいってきました。
まあ,担当例会なのですが、グループ・ディスカッションをやるわけではなかったので、グループ長でしたが質問のとりまとめ役でした。
しかし、とても対照的なふたりの報告できかせていただきました。
ひとりは、職人的家族経営を目指すということでしょうか。違うかもしれないので、自分の責任で書きたいと思います。
従業員の高齢化という課題がすぐ目の前にあり、問題解決の必要性に迫られている。新卒採用をしたうえで、多少ウィングを広げていく。
また、自社の強みというのが職人的作業にある、というようなことをいわれました。経営指針の発表会なので、本来、経営者としては、自分の頭にあるものをレビューにさらすわけですから、経営者としての深みも分かってしまいますし、怖いですね。でも、彼は心をベースにした経営、そして技術面などで妥協しないこと、ウィングを広げていくことを骨子に採用計画を練っていくという点が報告の骨子だったかな、と思っております。同族会社の場合、経営指針は従業員に夢を見させるためのものですから、なかなか現実的には建築関係で職場環境は厳しいでしょうが、良い会社、だからこそ長きにわたって継続してきたのだろうな、と思っています。
次の方は対照的ですが、やはり多くの専門家が入っているらしく飲食店経営のセオリーである仕入3割、人件費3割、利益3割的なものが守られている点がすごいな、と思いました。
そのために、専ら飲食の製造部門に関しては、様々な工夫をこらしていますし、地方都市に多くの雇用をもたらしており、社会貢献もあるな、というように思うのです。ただ、彼は、寿司屋ながら職人は目指さない、むしろマニュアル化を図ることによって、パートの方でも寿司を握るようにされたいということでした。といっても、おのずから、そのマニュアルはレベルの高いものになるだろうと思います。
とても、対照的な報告で、甲乙はつけがたいのですが、想いましたのは、やはり後者の会社は一日の売上把握もしているとのことで、飲食店経営の難しさというものが伝わってきますね。かなり割り切っている印象で報告をなされたのですが、現実には、かなり悩まれたうえで決めたのではないか、と想います。
経営指針は、前者の会社は従業員に夢をみさせたり経営者を鼓舞させたりするもの、後者の会社は、そうですね投資家説明用という印象を受けて用途も違うと感じました。
ただ、ワインと一緒で熟度の問題もあるから、前者の会社の方が楽しみというご意見もいただき、前者の会社の担当でしたので、そういう面では、うれしく受け止めました。
舛添知事が政治資金の私的流用疑惑を指摘され、辞任に追い込まれた。
本人は議会運営委員会で、リオデジャネイロの五輪には行かせてくれと涙ながらに訴えたという。
この人は、いったいどういうフィロソフィーで政治家をしていたのだろうか。
舛添氏は、そもそも、今回、対応を誤らなければ辞任にまでは追い込まれなかったが、ヤメ検の佐々木善三弁護士。
この方、東京電力で、社長の刑事責任を追及されることを防止するためにも登場した愉快な弁護士さんなのだ。
東京電力の際は、民主党に対するアゲインストが強く、依頼者の代理人を称して「第三者委員会」といっても通ったかもしれないが、今回はこれがあだ花になってしまった。
政治資金規正法に違反しますか、と聴いたら誰でも「違反しない」と回答するに決まっている。法律には使途の制限がないからで、行政法規に違反したという責任はとれるかもしれないが、客観的に法律に違反するかどうかは裁判所も認定してくれるわけではないので、あまり都民目線からみると重要ではない。
むしろ、大切なのは、信認関係を維持できるだけの信頼関係が保たれているかであると思う。第三者委員会と称した弁護士は、違法と信認関係を誤解し、結果的に舛添知事を辞任に追い込んでしまった、オウンゴールだったのかな、という印象が保たれません。違法か否かというのは、抜き差しならぬ関係になったときのジャッジメントの話しで、都民と抜き差しならぬ関係になった時点で知事と都民との信認関係は終わってしまいましたね。
しかし、ある意味、不相当ではあるが違法ではない、というのは、こどももまねしそうなダメな大人の典型的な言い分のようですね。中途半端に政(まつりごと)に足を突っ込むと、ピエロになってしまいますね。
僕も甥っ子のハルくんから、「不相当だけど違法じゃない」とかいわれたらどうしようと思ってしまいます(笑)
いろいろなニュースをみていると、少なくとも社会科学の世界では、どうも人々の分断が進んでいる、という印象が強くなってきた。
その典型的なものは、英国のEUからの離脱するか否かというイシューだろう。
イングランドでは離脱派が多く、もともと英国から独立したいスコットランドでは残留派が多い。
EU残留を支持していた女性議員が、BBCワールドによると、「ブリテイン、ファースト」と叫んだ右翼過激思想の持主に殺害された。
英国で議員が殺害されるというのは前代未聞のことだ。主には、移民の受け容れ量とユーロ非加盟国であるのにユーロ危機のとばっちりを受けたことが離脱論の背景にあります。
しかし、歴史は繰り返すもので、尊王攘夷運動と本質的には変わりません。たしかに、英国とフランスでは、アフリカ系の人に出会う回数が全然違うと感じましたしディダクションをかけているのだな、というのは肌で感じます。そして、ドイツもフランスも官僚組織が充実していますから、いわゆる中央官僚の焼け太り批判もイギリスにはあるのですね。しかし、今後、保護主義的ブロック経済で、イギリスをやっていかせるつもりなのだろうか、と考えると、開国に舵を切った日本の明治時代を思い出すものですね。TPP論争も本質的には同じ問題ですし、日本は移民をほとんど受け容れていないので、こういう論争からも分断されています。しかし、移民かどうかは別として人口が減少し高齢化が進む日本でも移民の受け容れは避けては通れない道ですが、イギリスは英語が通じる(当たり前ですが)お手軽な国ゆえに移民の問題は深刻なのかもしれません。
そして、アメリカのフロリダで起きたテロ。これは、ホモフォビアによる犯行とみられますが、確信犯(自分が正しいと信じて行う犯罪)的な犯罪は悲惨です。そして、アメリカ大統領選挙も移民排斥を叫ぶトランプ。もはや冷めたピッツァのクリントン女史。民主党内でもサンダース氏が負け戦を続け、混乱を長引かせています。
ところで、昔の政治家などは必ずしもフィロソフィが一緒でなければ仕事をしないというスタンスではなかったと思います。それが再統合なのだろうと。
いやに記者会見が多く、かつ、長い東京都知事。それでも石原知事は、記者の質問に答え続けましたし、基本的にスタンスの違いからどうという発言もあまりなかったように思います。そして、石原氏の盟友は元自民党左派の亀井氏。亀井氏も、記者クラブ制度が排外的として、外国人記者とフリーランサーのみのお茶会を開催し重要なことはそこでいうようにするなど、閉鎖的な人間や多角的に物事をみない人には終始、シニカルな対応を続けていたように思います。今は、信念が、信念が、と政治家に求めますが、あまり信念が大事すぎるとネゴシエーターとして機能しないのですよね。理想が同じでなければ、というものはいいのでしょうが、信念というのは本来、おのおのの人間がそれぞれ持つものですから、それを統合していくと、結局、白か、黒か、分断が進む社会へと進んで行ってしまいますね。
表現の自由もしかり。ヘイトスピーチを規制するといっても、抽象的な法律の場合、政治的イシューが「ヘイト」といわれることもあります。例えば、安倍政権の排外を主張している団体や沖縄でアメリカ兵の排外を主張する団体も「ヘイトスピーカー」といわれるリスクをよく考えていない。意見の再統合集約を目指すのが、自由な論評なのですが、分断が進んだうえに、なんでもかんでも「ヘイトスピーチ」といわれかねないものが少数派の政党から出されること自体、大局、見えていますか?と問いたいものです。
表現内容規制は極めて厳格な規制で臨むべきと憲法学では誰でも大学で習っているのですが、場当たり的な立法、局所的視点が多いという印象です。
1 本件は,宗教法人の問題でした。まあ、それでも財団法人と解してよいでしょう。
争点ですが、寄附行為に加えられた4件の変更の無効確認等を求める事案である。上記各変更のうち,特例財団法人から一般財団法人への移行時にされた2件の変更(判文中の本件変更2及び本件変更4)について,法人の同一性を失わせるような根本的事項の変更である場合には無効となるか否か等が争われたものです。まあ公益性もあるので、同一性を失わせるという理論的限界はあるのかという視座であるように思われるように考えるのが自然のように思います。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) Yは,大正元年,A宗の宗派であるB派の門徒らにより,旧民法に基づく財団法人として設立された。設立時のYの寄附行為には,①Yの目的について定める条項(以下「本件目的条項」という。)において,YはB派の維持を目的とするものと,②Yの解散に伴う残余財産の帰属について定める条項(以下「本件残余財産条項」という。)において,Yの解散に伴う残余財産はB派に寄附するものと,③Yの寄附行為は所定の手続を経てこれを変更することができるものとする定めがあった。
(2) Xは,昭和27年に宗教法人として設立され,B派の地位を承継した。
(3) Yは,平成20年12月,一般社団・財団法人法及び整備法の施行により特例財団法人となり,その寄附行為は定款とみなされた。さらに,Yは,平成23年2月,整備法45条の認可を受け,通常の一般財団法人に移行したが,この際,①本件変更2として,本件目的条項が,広く仏教文化を興隆する事業を行うことにより世界の精神文化発展に寄与すること等を目的とする旨に,②本件変更4として,本件残余財産条項が,Yの残余財産は類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨に変更された。
3 理論的には、まあ、定款のようなものを作るわけですが、旧民法では、寄付行為の変更ができないと我妻説は考えていたようです。
まあ、組合に近いという理解のように思われますね。そこで学説は,財団法人は,設立者の決定した根本規則に基づき理事が活動するだけであって,法人の活動を自主的に決定する機関を持たないことから,寄附行為は原則として変更することができず,ただ,寄附行為に変更の方法を規定している場合には,寄附行為の実行として変更が可能であるなどと解するのが通説的見解でした。
この見解に立てば、今回の判例は理論的に整合しない、ということになりそうです。
(2) 問題は、民法の法人の規定が削除され、新法に移行した点です。この点が新法の解釈として問題になったものと解されます。
一般財団法人の定款変更については,①目的並びに評議員の選任及び解任の方法に係る定款の定め(以下「目的等の定め」という。)を除き,評議員会の決議によって変更することができ(一般社団・財団法人法200条1項),②設立者が原始定款において目的等の定めを評議員会の決議により変更することができる旨を定めた場合には,評議員会の決議によってこれを変更することができ(同条2項),さらに,③設立当時予見することのできなかった特別の事情によって,目的等の定めを変更しなければ運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは,裁判所の許可を得て,評議員会の決議により,これを変更することができるとされている(同条3項)。立案担当者は,①,②のとおり目的等の定めの変更の可否を設立者の意思に委ねたことにつき,一般財団法人は設立者の定めた目的を実現するための法人であり,その運営等の根幹部分につき設立者の意思が尊重される仕組みとすることが相当と考えられるからであると,また,③につき,そのような場合にも定款変更を一切許容しないとすれば,かえって法人運営の機動性・柔軟性を阻害するため,定款変更を認めることがむしろ法人の設立者の合理的意思にも合致すると考えられることから定款の変更が認められると,それぞれ説明している。
(3) 結局、立案担当者は,特例財団法人が一般財団法人へ移行するためには定款変更が不可欠であることから,これを可能とする手続を規定したものであると説明していますので、そうなるのではないか、と。(前掲一問一答258頁等)。
5 以上を前提に本件を検討すると,特例財団法人の定款変更については,論理的には,①旧民法の規定に基づく財団法人の寄附行為の変更に関する通説と同様に,財団の設立者が定款の定めによってどの範囲の変更を許容しているかという観点から判断する見解と(原審も,その判断の根拠を設立者の意思に求める点で,この見解と同様の考え方を基礎とするものといえる。),②整備法の規定どおり,特段の制約はないものとする見解とが考えられるように思われる。
特例財団法人が一般財団法人に移行するに当たっては,
①旧民法の規定に基づく財団法人の寄附行為の記載事項(旧民法37条)と一般財団法人の定款の記載事項(一般社団・財団法人法153条等)とは異なるから定款変更が不可欠であること
②特例財団法人は公益目的支出計画の作成及び実施を義務付けられているところ,現在の目的が公益目的事業とはいい難いため公益目的の支出のための事業ができない場合や,現在の目的に従って上記事業を行うだけでは実効性のある公益目的支出計画が作成,実施できない場合等には,設立者の意思等にとらわれずに目的を変更することが必要となり得るところである。また,整備法では,特定財団法人において,必要ならば定款変更に関する規定を自ら整備した上で,定款変更ができる旨が規定されており,他方,特例財団法人の同一性を失わせるような根本的事項に関して定款の変更が許されない旨を定めた規定は存在しない。つまり、かえてもよいよ、、とこれを妨げる条文がないということですね。
結論としては、制定法準拠主義になってしまいますが、特例財団法人の定款の変更に明文にない制約があると解することはできません。
そうすると,特例財団法人は,目的等の定めを含む定款の変更について,その同一性を失わせるような根本的事項の変更であるか否かにかかわらず,その判断によりその定款の変更をすることができるものと考えるのが相当と解されます。
第2 上告代理人桂充弘ほかの上告受理申立て理由第4について
1 所論は,整備法の規定に基づく特例財団法人の定款の変更において,当該法人の同一性を失わせるような根本的事項の変更は許されないとした原判決の前記第1の3(2)の判断には,法令の解釈を誤る違法があるというのである。
2 特例財団法人は,一定期間内に公益法人認定法の規定による公益財団法人への移行の認定又は通常の一般財団法人への移行の認可を受けなかった場合には,上記期間の満了の日に解散したものとみなされる(整備法44条から46条まで)ところ,旧民法の規定に基づく財団法人の寄附行為の記載事項(旧民法37条)と公益財団法人又は通常の一般財団法人の定款の記載事項(一般社団・財団法人法153条等)とは異なる部分があるから,特例財団法人が公益財団法人又は通常の一般財団法人へ移行する場合には,定款の変更が不可欠である。また,特例財団法人が通常の一般財団法人に移行するためには,解散するものとした場合における残余財産の額に相当する金額を公益の目的のために支出するための計画を作成して実施しなければならないとされるが(整備法119条1項,123条1項),このような計画を作成するために特例財団法人の目的に係る定款の定めを変更しなければならない場合も少なからずあり得るものと考えられる。
そして,整備法は,特例財団法人の定款の変更に関する経過措置等を定めているところ,これによれば,評議員を置く特例財団法人(以下「評議員設置特例財団法人」という。)は,目的並びに評議員の選任及び解任の方法以外の事項に係る定款の定めについて,評議員会の決議によってこれを変更することができるほか,目的並びに評議員の選任及び解任の方法に係る定款の定めについても,評議員会の決議によって,一般社団・財団法人法200条3項の規定によることなく,これを変更することができる旨を定款で定めることで変更することができるとされている(一般社団・財団法人法200条1項,整備法94条4項において読み替えて適用される一般社団・財団法人法200条2項,整備法94条5項)。また,評議員設置特例財団法人を除く特例財団法人には,一般社団・財団法人法200条の適用がなく,その定款に定款の変更に関する定めがある場合には,当該定めに従い定款の変更をすることができ,上記定めがない場合には,定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をした上で,当該定めに従い定款の変更をすることができるとされている(整備法94条1項から3項まで)。他方,整備法には,特例財団法人の同一性を失わせるような根本的事項に関する定款の変更が許されない旨を定めた規定は存在しない。
そうすると,特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるものというべきである。このように解することは,先に述べた定款変更の必要性に沿うものであり,また,旧民法の規定に基づく財団法人から通常の一般財団法人への移行を円滑かつ適切に行うための措置を定める整備法の趣旨にも合致するものである。
3 これを本件についてみると,本件変更2及び4は,特例財団法人である上告人において,本件変更条項に従ってされたものであるから,整備法94条2項に基づく定款の変更として有効というべきである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。
第3 上告代理人桂充弘ほかの上告受理申立て理由第3について
前記第2の説示に照らすと,本件変更4がされる前の本件残余財産条項の内容がいかなるものであったとしても,本件変更4が有効であるから,本件変更3の無効確認を求める利益はない。そうすると,本件変更3の無効確認請求に係る被上告人の訴えは却下すべきものである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。
第4 職権による検討
前記第2の説示に照らすと,本件変更2がされる前の本件目的条項の内容がいかなるものであったとしても,本件変更2が有効であるから,本件変更1の無効確認を求める利益はない。そうすると,本件変更1の無効確認請求に係る被上告人の訴えは却下すべきものである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
第5 結論
以上によれば,原判決中,本件各変更の無効確認請求に関する部分はいずれも破棄を免れず,同部分につき第1審判決を取り消し,本件変更1及び3の無効確認請求に係る被上告人の訴えを却下し,本件変更2及び4の無効確認請求を棄却すべきである。
4 本判決
この判決は、ざっくりいうと、特別利害関係人が参加して、多数決が行われたのですが、その場にいる存在感から心理的圧力を受ける可能性も否定することはできないという見解も成り立ち得るところです。したがって、単純に頭数の問題に還元して良いのかな、という印象を持ちます。
最高裁判所第二小法廷は、漁業協同組合の理事会の議決が、当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても、当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは、その効力は否定されるものではないと解するのが相当であると判示し、本件漁協の理事8名から特別の利害関係を有する理事2名を除外した6名の過半数に当たる4名が出席してその全員が賛成してされた本件貸付けに係る理事会の議決は、無効であるとはいえないとして、同議決が無効であることから本件支出負担行為等は町長の裁量権の範囲を逸脱してされたものとして違法であるとした原判決の被告敗訴部分を破棄し、原告が他に主張する本件支出負担行為等の違法事由の有無等について審理を尽くさせるため、上記の部分につき本件を原審に差し戻す旨の判決をした。
原判決は、本件議決に特別の利害関係を有する理事が加わったという瑕疵があることのみを理由として本件支出負担行為等が町長の裁量権の範囲を逸脱したものであると判断しており、原告が本件支出負担行為等が違法であるとして主張する他の事由について審理、判断をしていないことから、本判決は、これらの他の事由についての審理、判断を尽くさせるために本件を原審に差し戻すこととしたものと解される。
5 本判決の判断について
本件は、特別の利害関係を有する理事が加わった漁業協同組合の理事会の議決の効力という論点に関して水産業協同組合法37条2項の解釈が争われた事案であるが、同項の規定は、株式会社の取締役会決議に関する会社法369条2項の規定と同旨のものであり、上記論点に関しては、特別の利害関係を有する取締役が加わった取締役会決議の効力という会社法上の論点において論じられているところと同様に論ずることができるものと考えられる。
この会社法上の論点について、学説においては、上記のような取締役会決議は、常に無効であるとする見解、原則として無効であるが、この瑕疵がなくても決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは有効となるとする見解、特別な利害関係を有する取締役を除いてもなお決議の成立に必要な多数が存在する場合は原則として有効であるが、当該取締役が出席して決議に不当な影響を与えたといった事情がある場合には無効となるとする見解、特別な利害関係を有する取締役を除いてもなお決議の成立に必要な多数が存在するならば決議の効力は妨げられないとする見解などがみられる。
また、判例は、最二判昭和54・2・23民集33巻1号125頁、本誌570号3頁(以下、「昭和54年最判」という)が、中小企業等協同組合法に基づく企業組合の理事会決議に特別の利害関係を有する理事が加わった場合であっても、当然に無効ではなく、その理事の議決を除外してもなお決議の成立に必要な多数が存するときは、決議としての効力を認めて妨げないと解すべきであると判示しているが、特別の利害関係を有する理事が参加した企業組合等の理事会決議に関する規定である当時の中小企業等協同組合法42条は、昭和56年法律第74号による改正前の商法239条5項の規定を準用する旨定めていたところ、同項は、「総会ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ズ」と定めるものであり、現行の会社法等の規定とは文言が異なっていることなどから、現行の会社法等の下においても昭和54年最判と同様に解すべきであるかどうかは必ずしも明らかではなかった。
このような状況のもとで、本判決は、特別の利害関係を有する理事が理事会の議決に加わることができない旨を定める水産業協同組合法37条2項の趣旨が、理事会の議決の公正を図り、漁業協同組合の利益を保護するためであると解されることなどを説示し、昭和54年最判と同様に、特別な利害関係を有する理事を除いてもなお議決の成立に必要な多数が存在するならば議決の効力は妨げられないとする見解を採ったものである。
しかし、やはり、公正さが疎外される特段の事情があるのであれば、無効とするべきように思われ、判旨には賛成することはできません。
本判決は、株式会社の取締役会の決議に関する論点と同様に論ずることができるものであり、特別の利害関係を有する取締役が加わってされた株式会社の取締役会決議の効力についても、本判決と同様の考え方が採られることになると考えられることなどからして、本判決は重要な意義を有するものと考えられるだけに深刻な問題提起です。
(1) 水産業協同組合法37条2項が,漁業協同組合の理事会の議決について特別の利害関係を有する理事が議決に加わることはできない旨を定めているのは,理事会の議決の公正を図り,漁業協同組合の利益を保護するためであると解されるから,漁業協同組合の理事会において,議決について特別の利害関係を有する理事が議決権を行使した場合であっても,その議決権の行使により議決の結果に変動が生ずることがないときは,そのことをもって,議決の効力が失われるものではないというべきである。
そうすると,漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和50年(オ)第326号同54年2月23日第二小法廷判決・民集33巻1号125頁参照)。水産業協同組合法37条2項と同旨の定めであるA漁協定款49条の3第2項についても,同様に解するのが相当である。
(2) これを本件についてみると,本件議決に加わった理事のうち,Bは本件貸付けに係る被害漁業者の経営者であり,同人の子であるCは本件貸付けに係る貸付金を原資としてA漁協から融資を受けた者であるから,いずれも本件議決につき特別の利害関係を有するものというべきである。しかし,本件議決については,A漁協の理事8名からこれらの者を除外した6名の過半数に当たる4名が出席し,その全員が賛成したのであるから,特別の利害関係を有する理事を除いてもなお議決要件を満たすということができる。なお,水産業協同組合法37条1項によれば,本件議決につき定足数が満たされていることは明らかである。
そうすると,本件議決を無効とすべき瑕疵があるとはいえない。
(3) そして,本件規則が効力を生じていないものであっても,本件規則に基づく貸付けと同様の目的を有する貸付けをするに当たり漁業協同組合の理事会の議決を要するものとすることは合理的なものであるところ,上記のとおり,本件議決を無効とすべき瑕疵があるとはいえないことからすれば,結局,Dは,本件貸付けを合理的なものと認められる手続によって行ったものということができ,この点に関し,本件支出負担行為等が町長の裁量権の範囲を逸脱してされたものということはできない。
5 以上と異なる見解に立って,本件支出負担行為等が町長の裁量権の範囲を逸脱してされたものであって違法であり,Dは損害賠償責任を負うとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,被上告人が他に主張する本件支出負担行為等の違法事由の有無やこれに関連して損害が東洋町に発生しているといえるか否か等について,更に審理を尽くさせるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。
その理由は,次項のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,5頁19行目の「平成25年」を「平成26年」に改める。
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1) 本件雇止めの時点で,控訴人は本件配送業務に従事することができたとする点について
ア 控訴人は,2kg以上の物を持てるのは3か月後であるとする本件パンフレットは,腱板断裂手術を受けた全患者に一律に交付されるものであると主張し,A医師の回答書(甲31)には,これに沿う記載がある。しかし,A医師は,平成26年3月27日にB支店長やDと面談した際,同医師の所属する病院のスタッフが,腱板断裂手術を受けた患者に対し,再断裂の可能性をゼロにするために少なくとも1年間くらいは,力仕事はしないようお願いしている等,本件パンフレットの記載(重労働は1年間極力避ける。乙3・4丁目)に沿う発言をしており(甲11・35頁),本件パンフレットの内容が控訴人に妥当しないとはいえない。
また,控訴人は,控訴人の腱板断裂は幅2.5cm,奥行き3.0cmで,中断裂(断裂の幅と奥行きが3cm×3cm以下のもの)に分類されるものであることを前提に,本件パンフレットの記載は,中断裂の腱板断裂手術を受けた者にとっては必要以上の配慮をするものであると主張し,E医師の意見書(甲32。以下「E意見書」という。)の中にはこれに沿う部分も存在する。しかし,E意見書は,小断裂・中断裂の患者で手術が順調に行えたという前提の下で,2kg以上の物を持てるのは3か月後であるとする本件パンフレットを厳しすぎるとしているにすぎず,また,あくまで一般論であると断っているのであって,これをもって控訴人の主張を裏付けるには足りない。かえって,E意見書は,術後3か月半で10kgのものを両手で持ち上げることができても必ずしも驚かないとしつつも,持ち上げないことに越したことはないとも明記しているのであって,E医師が,10kgのものを仕事上日常的に持ち上げるような事態は控訴人のような状況にある者にとって危険であると考えていることがうかがえる。
イ 控訴人は,A医師は,被控訴人から本件配送業務について,実際に想定されている作業よりも過大に説明を受けているにもかかわらず就労が可能であるとの結論に至っていると主張する。
しかし,Dの説明が過大であるとは認められず(甲11の36頁では,台車を押していくことを前提に「百何キロぐらいある?」との発言もあるが,100kgを超えるものを持ち上げると説明したとは読み取れない。),また,A医師は,それを受けて「可能性でいえば,切れない可能性ももちろん高いでしょうし,切れる可能性もありますけれどもという,就労自体はできると思いますよね。」という発言はしているが(同37頁),力仕事は,すればするだけ再断裂のリスクが上がることも認めており(同38頁),控訴人の就労可能性については,シフトを変える等により就労させることを想定していたとも述べているのであって(同40頁,42頁),従前から控訴人が従事していた本件配送業務そのものを想定してそれが可能であると考えていたとは認められない。
さらに,控訴人は,再断裂の可能性は限りなく低かったと主張するが,A医師の補足意見(甲30)中の「医師として総合的に判断し再断裂の可能性はゼロではありませんが,決して高くはなかったため,従前の職務に復職可能であると診断しました。」との記載が,再断裂の可能性が限りなく低いとの趣旨とは理解できない。
以上を総合すると,本件雇止めの時点で,控訴人には従前の職務に復帰することによって一定の割合で左肩腱板再断裂のリスクがあったと認められるのであり,控訴人が本件配送業務に復帰可能な状態にあったとの控訴人の主張は採用できない。
(2) 控訴人は,被控訴人には,控訴人の当直業務への配置可能性を検討すべき義務があったとして種々主張するが,いずれも採用できない。
ア 控訴人は,就業規則上勤務箇所や職場の変更が可能とされていたと主張する。
しかし,控訴人と被控訴人の雇用契約上は,職種は本件配送業務に限定されていたことは争いがないのであるから,被控訴人に,控訴人の職種を変更して雇用を継続するよう配慮する義務があるとはいえない。
イ 控訴人は,控訴人を当直業務に配置換えをすることは可能であり,現にB支店長もこれを検討していたと主張する。
(ア) 補正の上引用した原判決2頁5行目から9行目,16行目から18行目のとおり,平成23年3月17日付け雇用契約書(甲3の13)における「従事すべき業務の内容」欄に「当直及び営業」との記載がなされたこともあったが,平成25年9月26日の最後の更新の際は,雇用契約書上,「従事すべき業務の内容」欄に「配送(それに付随する業務全般)」と記載されている。
これを前提として検討するに,証拠(乙7)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人における当直業務は,売上金収納,釣銭準備金の用意,緊急時の商品発注手配等の緊急時の対応,金銭の管理,商品入荷の確認と在庫管理,電話対応など,性質上配送業務に付随するとはいえない業務も含まれていることが認められるのであり,控訴人を当直業務に従事させるとすれば,上記契約における職種の変更をしなければならないし,また,当直業務の実態は,配送業務を主な業務とする者が月2回ないし4回程度の当直業務を行うにすぎないものであったことが認められるのであるから,被控訴人において,職種変更を伴い,また,専従者を配置する必要性も認められない当直業務に控訴人を配置換えすることが可能であったとはいえない。
(イ) また,弁論の全趣旨によれば,B支店長が,平成25年12月ころ,控訴人に対し,平成26年2月の復帰が可能であることを前提に,当直業務への補助的業務に従事させることを検討する旨の発言をしたことがあることは認められるが,これは,その文脈からみて,好意による特別の配慮を検討する旨述べたにすぎないことが明らかであり,また,前提となる平成26年2月の控訴人の職場復帰は実現しなかったのであるから,上記発言を根拠に被控訴人に控訴人を当直業務に配置する義務があったとはいえない。
ウ 控訴人は,肩腱板断裂は労働災害であり,雇止めの可否については慎重に検討すべきであると主張するが,控訴人において労働契約で限定された職務の遂行が困難である上,上記イ(ア)のとおり,当直業務は独立の配置換えの対象となるような業務とはいえないなど,本件における事情を総合すると,労働基準法19条1項の解雇制限の趣旨が本件のような場合にまで及ぶとはいえない。
エ 控訴人は,被控訴人としては,平成26年3月31日の時点で雇止めの可否を早急に判断するのではなく,1度は契約を更新した上で,経過観察のため休職期間を延長すべきであったと主張するが,このような義務を発生させる法的根拠があるとは認められず,採用できない。
(3) 控訴人は,被控訴人が,既に何回も腰痛を発症して休職しているCに対しては,車内販売等他の業務に就かせることも検討しており,平成26年3月に直ちに雇止めはせず,いったん更新をした上で同年9月に雇止めをしていることと対比して,控訴人に対して同じ措置を執らずに雇止めをした真の目的は,本件組合の委員長である控訴人を嫌忌し,これを排除するという不当なものであったことは明らかであると主張する。
しかし,Cと控訴人では疾病の内容,その他の事情が異なるのであるから,その対応を異にしたことをもって直ちに控訴人主張の不当な目的を推認することはできないし,その他被控訴人が控訴人に対し雇止めをしたのが,控訴人の組合活動を嫌忌したことによるものと認めるに足りる証拠はないのであって,控訴人の主張は採用できない。
3 結論
したがって,控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高裁平成28年3月28日は、会計帳簿の閲覧謄写の請求について、関連会社に対する会社の不必要または不適切な財貨の移動がされていないかを確認する必要がある、会社の代表取締役に対する責任追及を行う必要がある、取締役の利益相反取引の有無を明らかにする必要がある場合、その請求の理由の内容は具体的であるとしています。
東京地裁平成28年4月18日は、要するに家賃を2カ月滞納した賃借人に対して、補助キーを取り付けて追い出し行為を行った。
この点、物件への立ち入りを強制的に遮断する行為につき不法行為責任を認めている。
また、物件内に立ち入る行為も、窃盗罪又は器物損壊罪に処せられるべき不法行為としました。
財産的損害 30万円
精神的損害 20万円
弁護士費用 5万円
日本経済新聞の取材によると、30年後に中小企業消滅という記事が躍った。
びっくりした人もいたのではないか、と思うが、要するに、「円滑な事業承継や若者の起業が進まなければ30年には80歳前後に達し、いまの男性の平均寿命とほぼ並ぶ」ということで、中小企業経営の経営者が年老いてしまうというストーリーだ。
ただ、日経新聞がいうほどに後継者不足になっているのだろうか。自分が青年会議所、青年同友会に所属していると後継者や若手企業者も多いので、自分の感覚と違うなあと記事をながめたのです。
たしかに、後継者は、親族以外には出せないので、同族会社の事業承継は難しい。日経新聞が指摘するように、「技術や設備、商標は韓国企業に引き渡した」とあるが、清算処理の一環かもしれないな、と思います。しかし、借金を返せるうちに自主的に廃業するということはネガティブなことではありませんね。
たしかに、今回同友会でプロジェクトでの報告者は、後継者。採用を軽視していたこともあり、後継者を除くと60歳を超える人が多く、世代を継いで技術を継承していくということを経営指針にして社内で発表され、同友会でも発表されるようです。
ただ、日本は中小企業経営が9割以上。中小企業経営なしでは日本経済は決してなりたちません。大企業と中小企業についてみると、やはり就職先の人気も偏ってしまいますし、収益性も全然違ってきている、という面があります。製薬会社が良い例ですが、収益性が高く大企業がM&Aをして、中小企業をのみ込んでいく姿は、個人的に日本社会にとって良いのかな、という気持ちを抱きます。
事業承継を待つばかりでなく、若者の起業を促すことも有効な手立てになる。僕は、ドリームゲートアドバイザーをしていて、起業の支援もしています。ただ、そもそも、事業それ自体が違法ではないことから躓くところもあります。弁護士のリーガルチェックも大事ですね。
起業とその5年後生存率ということもあり、なかなか起業される例が、少なくなってしまうところもありますね。中小企業の30年後がなくなる、というよりも、それは先人の起業の結果であり、現在の人たちがどんどん起業できる外部環境を整備をアベノミクスのステージにも載せて欲しいですね。
最高裁平成27年3月26日が、非上場株式の評価について判断を示しています。
本件は,Yを吸収合併存続株式会社,Aを吸収合併消滅株式会社とする吸収合併に反対したA株主のXが,Aに対して株式買取請求権を行使し,会社786条2項に基づいて価格の決定の申立てをした事案である。弁護士からは肯定的意見が多いようであるが、公認会計士からは非上場であるのに非流動性を考慮しないのは釈然としないとの意見が寄せられている。この判決は、裁判所の合理的裁量に一定の制約を課すものと思われ実務上の意義を有すると思われる。
Aは非上場会社であるところ,原審(札幌高決平成26・9・25,平成26年(ラ)第151号)は,収益還元法(将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定する方法)を用いてA株式の買取価格を決定するにあたって,市場性がないことを理由とする25%の減価を行った(非流動性ディスカウト)。
しかし本決定は,①非上場会社の株式の買取価格を決定するにあたり,どのような場合にどの評価手法を用いるかについては,申立てを受けた裁判所の合理的な裁量に委ねられている,②しかし,一定の評価方法を合理的であるとして,当該評価方法により株式の価格の算定を行うこととした場合において,その評価手法の内容・性格等からして,考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定することは許されない,③非流動性ディスカウントは,非上場会社の株式には市場性がなく,上場株式に比べて流動性が低いことを理由として減価をするものであるところ,収益還元法は,当該会社において将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定するものであって,同評価手法には,類似会社比準法等とは異なり,市場における取引価格との比較という要素は含まれていない,④吸収合併等に反対する株主に公正な価格での株式買取請求権が付与された趣旨が,吸収合併等という会社組織の基礎に本質的変更をもたらす行為を株主総会の多数決により可能とする反面,それに反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに,退出を選択した株主には企業価値を適切に分配するものであることをも念頭に置くと,収益還元法によって算定された株式の価格について,同評価手法に要素として含まれていない市場における取引価格との比較により更に減価を行うことは相当でない,と判示して,非流動性ディスカウントを行う前の価格を買取価格として決定した(破棄自判)。
本決定は,会社786条2項に基づいて非上場会社の株式の価格を決定するにあたって,非流動性ディスカウントを考慮することができるかにつき,最高裁が初めて判断を示したものである。この点に関しては,東京高決平成22・5・24(平成20年(ラ)第637号)が,「株式買取請求権は,少数派の反対株主としては株式を手放したくないにもかかわらずそれ以上不利益を被らないため株式を手放さざるを得ない事態に追い込まれることに対する補償措置として位置付けられるものであるから,…非流動性ディスカウント…を本件株式価値の評価に当たって行うことは相当でない」と判示した一方で,本件の原審のように非流動性ディスカウントを考慮するものもあり,実務は統一されていなかった。また,学説においては,「取引相場のない株式等は,簡単に譲渡できない分だけ上場会社の株式に比して経済的価値が低く,したがって,割引率として後者〔上場会社〕に関係する数値を用いた場合には,算出された金額をいくらか減価することにより調整すべきである」との見解も有力であった(江頭憲治郎『株式会社法〔第6版〕』19頁)。
収益還元法は,将来の各期の純利益を現在価値に割り戻し,その総和をもって企業(=株式)の価値を算定するものであって,売却による価値の実現化はこの評価手法のもとでは予定されていないのであるから,理論的には本決定の説くとおり,非流動性ディスカウントを考慮するのは相当ではない。しかし他方で,上記の有力説の指摘もまた傾聴すべき点を含んでおり,本決定を前提とした場合には,今後,非上場会社株式の価格の算定にあたって割引率の妥当性がより厳密に問われることになろう。
以上のとおり,本決定は,従来は不統一であった論点について最高裁がはじめての判断を示したものとして,実務上大きな意義を有するものである。
会社法786条2項に基づき株式の価格の決定の申立てを受けた裁判所は,吸収合併等に反対する株主に対し株式買取請求権が付与された趣旨に従い,その合理的な裁量によって公正な価格を形成すべきものであるところ(最高裁平成22年(許)第30号同23年4月19日第三小法廷決定・民集65巻3号1311頁参照),非上場会社の株式の価格の算定については,様々な評価手法が存在する.。
しかしながら,どのような場合にどの評価手法を用いるかについては,裁判所の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。
しかしながら,一定の評価手法を合理的であるとして,当該評価手法により株式の価格の算定を行うこととした場合において,その評価手法の内容,性格等からして,考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定することは許されないというべきである。
非流動性ディスカウントは,非上場会社の株式には市場性がなく,上場株式に比べて流動性が低いことを理由として減価をするものであるところ,収益還元法は,当該会社において将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定するものであって,同評価手法には,類似会社比準法等とは異なり,市場における取引価格との比較という要素は含まれていない。
吸収合併等に反対する株主に公正な価格での株式買取請求権が付与された趣旨が,吸収合併等という会社組織の基礎に本質的変更をもたらす行為を株主総会の多数決により可能とする反面,それに反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに,退出を選択した株主には企業価値を適切に分配するものであることをも念頭に置くと,収益還元法によって算定された株式の価格について,同評価手法に要素として含まれていない市場における取引価格との比較により更に減価を行うことは,相当でないというべきである。
したがって,非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことはできないと解するのが相当である。