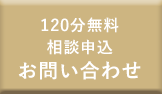取締役の一斉退職と新会社の設立
A会社の取締役が突然一斉に退職して、B社を設立して,旧会社Aと同じ商品をAと同じ得意先に販売したことは共同不法行為になりますか。また,B社に対しても責任は追及できるのでしょうか。
この点については、東京地裁昭和51年12月22日の判決がありますので,紹介します。
結論的には共同不法行為になる、B社に対しても責任は追及できないというものですが,限界事例を認めたものと考えられます。したがって,あまり,この裁判例の射程距離を拡張することはできないでしょう。
たしかに,取締役や従業員は,在任中は競業避止義務を負いますから競業なんて論外ということになりますが,日本の裁判所は,契約終了後の競業会社設立にはおしなべて寛容な態度をとっています。つまり、契約は終了したので終了後をしばることは論理的にできないという形式的理由だけではなく、経済的自由競争の範囲であるとか、生活もかかっているからといった理由が実質的妥当性を支えています。
さて、本件では、B社はA社の得意先にアプローチを重ね同じ自動車用価額製品を販売し利益を上げました。これに対して、A社は、旧取締役及び従業員の担当領域での売上がゼロになってしまい、その営業は停止し事実上倒産状態になってしまいました。また、A社を通じて、商品を販売していたZ社までも経営が苦しくなってしまいました。
一般論の確認です。一般論は、既存の会社と同種の会社を設立して、同種の商品を販売することは原則として自由です。しかし、既存の会社の営業活動を違法に侵害するときには不法行為を構成するというべきです。判決では,著しく信義を欠き、もはや経済的自由競争として許される範囲を逸脱した違法があるとして、共同不法行為を認めました。そして、損害額としては、昭和46年4月から昭和47年8月までの売上減少による損害118万1315円などを損害として認定しました。
この判決は、委任・雇用終了後にも一定の範囲において、信義則上の競業避止義務があるとされたものとして,同様の営業活動の制限があると認めたものです。
以下、不法行為と認定されたポイントです。
・両者の商品は競合する
・両者の競合する商品は売上の4割を占め重要である
以下、判例の定立したルールです。
・Aにおいても、営業を継続してきたのであって、同営業活動を違法な手段・方法によって侵害されないという意味では法的保護の対象になる
・Bらの自由もAの営業活動を違法に侵害しない限り自由というにとどまる
・被告個人は設立にあたり、必要以上の損害を与えないように退職の時期を考える、相当期間をおいて予告する、製品選定などで配慮することが当然要請される
・いたずらに自らの利益のみを求め他を顧みないということは許されない
以下、判例が認定した事実のポイントです。
・在職中から新会社設立を企図していた
・突然しかも一斉であること
・A社の得意先に同じ商品の販売を始めた
さて、問題は、B社に責任があるかということです。現在の裁判例においても、競業した人が悪いことは分かるが、当然にB社も連帯して共同不法行為者として賠償責任を負うという明示的な裁判例はありません。
そこで、裁判例はどのように述べているのでしょうか。
・被告会社が,原告会社と競業する商品を販売するだけでは、違法な行為ではないが、不公正な方法で競合する製品を販売し、同社の得意先を奪うこと、すなわち、会社設立前からの被告個人らの一連の行為が全体として違法性を帯びると評価される。そして,被告個人らの右行為は、被告会社の職務を行うためになされたものとは認められず、被告会社は不法行為責任を負わない。
とされてしまいました。
つまり、B社は賠償責任を負わないということです。これでは、B社の口座を差し押さえることはできませんから、個人に対する強制執行は不発に終わることも多く、実質的救済の観点から、B社の責任を認めた裁判例には疑問があります。もっとも、判旨を前提とするところ、「職務を行うためになされたとは認められない」としているので、職務を行うためになされたことを論証すれば良いのではないかという道筋も見えてきます。この点、B社設立後において、B社のA社の加害行為とみなされる行為は存在するのではないかとも思いますので、このあてはめが正しいのか疑問があります。
次に、損害額はどのように算定しているのでしょうか。
・少なくとも被告個人らは、昭和46年4月、5月、6月において、前年の同時期と同程度の売上を得たものと考えられるので、これに対する同社の純利益に相当するもの
・そして、売上高に対する利益率は7.5パーセントと認められる
このように個人責任を追及することはたやすいようですが、顧客名簿の流用があると予測される事案について、新設会社の責任が否定されているのはポイントであると思われます。