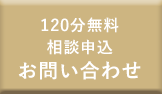仮装行為の否認
課税要件事実の認定にあたっては、私法行為の読み替えが問題になります。
税庁側からすれば「仮装行為」といわれていますが、税庁は、立論が手伝ってくれないので、それを後から反駁され裁判所もそれに沿った認定をされてしまうとたまりません。
中には、微妙と思われるものについては「仮装行為」とされています。
仮装行為というのは、意図的に真の事実や法律関係を隠ぺいないし秘匿して、みせかけの事実や法律関係を仮装することであって、通謀虚偽表示がその典型とされていると考えられる。
たしかに、理論的には実態に即した事実認定がなされるべきですが、行政裁判の事実認定の場合では、行政庁には裁量権があり、その事実の基礎が欠落しており、その裁量権を著しく逸脱・濫用する場合には違法になる、とされる場合がありますが、私見は民事の法律構成に、まったく裁量権がないというのはおかしいのではないかと思います。特に、税法は刑事法の認定に近いように思うのですが、国の課税につき裁量が認められないことは当然だと思います。しかし、私的自治の原則が支配する民法の世界に割り込んでくるというのは、通謀虚偽表示の要件を満たす場合に限られるというべきように思います。
否定例は枚挙に暇がないところですが、子会社によるノウハウ等の譲渡について、親会社による譲渡を仮装するものではないと認定したものがあります。名古屋地判平成17年9月29日判例タイムズ1256号81頁があります。
1 通謀虚偽表示の認定における間接事実について
本件における争点は,前記のとおり,本件資金移動が法人税法22条2項所定の受贈益に該当するか否かであり,その論理的前提問題として,本件譲渡契約が仮装された無効のものか,すなわち,原告とHRDとの間で民法94条1項の通謀虚偽表示が成立したかが争われている。
ところで,通謀虚偽表示の成立要件である,法律行為の当事者が当該法律行為(の表示行為)に対応する内心的効果意思を持たず,かつ持たないことにつき相手方と通謀したことは,それが専ら主観的な要素から構成されるため,それを推測させる客観的な事実,すなわち間接事実によって証明されることが通常であるところ,譲渡契約における目的物が譲渡人に帰属していないことは,これによって直ちに当該契約の無効を来すものではない(他人物売買も有効に成立することはいうまでもない。)ものの,そのことが前提とされて契約が締結されたなどの事情が認められない限り,一般的には不自然な契約であるといわざるを得ず,この意味で,売買契約の性質を有する本件譲渡契約によって譲渡の目的物とされた本件ノウハウ等が原告に帰属していたか否かは,有力な間接事実として,上記争点についての判断に大きな影響を与えるというべきである。この意味で,被告が本件譲渡契約が仮装されたものであることを証するために,本件ノウハウ等の帰属を問題としているのは,的確な対応というべきである(そして,本件各フランチャイズ契約におけるフランチャイザーがだれかは,本件ノウハウ等の帰属についての判断に影響を与える再間接事実に位置づけられるから,この問題も争点の判断に影響を与え得ると考えられる。)。
もっとも,上記争点の判断に影響を与える間接事実としては,目的物の帰属のほかにも種々考えられるところ,通謀虚偽表示は,内心的効果意思が存在しないにもかかわらず,通謀の上,あえて表示行為を行うのであるから,経験則上,そのような仮装行為をするについての動機が存在するのが通常と考えられる。すなわち,通謀虚偽表示が成立する場合には,当事者双方ないし少なくとも一方が,当該法律行為が有効に成立したという外形を作出することによって何らかの利益を得る関係が存在すると考えられ,逆にいえば,そのような動機が全く見当たらないという事実は,通謀虚偽表示の認定について,消極的な方向で作用することは当然である。したがって,被告の主張するように,租税回避等の経済的動機が存在しないからといって,直ちに本件において通謀虚偽表示が成立しないと断定できるわけではないとしても,かかる事情を無視ないし軽視することも相当とはいえない。
2 本件各フランチャイズ契約におけるフランチャイザーについて
被告は,本件各フランチャイズ契約におけるフランチャイザーが一条工務店であることから,同契約において供与される経営システムを保有しているのは一条工務店であり,したがって,本件譲渡契約締結当時にそれらが集積されて成る本件ノウハウ等も一条工務店に帰属する旨主張するのに対し,原告は,本件各フランチャイズ契約におけるフランチャイザーは原告であり,経営システムの保有者も原告である旨主張するので,まずこの点について判断する。
(1)フランチャイズ契約の特色とフランチャイザーの資格について
フランチャイズ・システムは,比較的歴史の浅い,新しい事業形態であるため,様々な内容のものがあり,フランチャイザーからフランチャイジーに対してなされる給付についても,営業標章の使用許諾,事業経営システムの付与,経営指導・統制,営業を行う権利の付与,商品や原材料の販売・供給などの一部又は全部が組み合わされ,フランチャイジーからフランチャイザーに対する義務についても,契約金・保証金・ロイヤリティの支払,営業への専念義務,経営システムの秘密保持義務などの一部又は全部が組み合わされるといったように多種多様な要素から成っているなど,フランチャイズ契約については,どの側面を重視するかによって,様々な定義が可能であり,定まったものはないとされている。もっとも,その典型的な内容については,ある程度の共通認識が形成されている。
例えば,社団法人日本フランチャイズチェーン協会が昭和47年に策定し,昭和54年に改定した定義は,「フランチャイズとは,事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が,他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び,自己の商標,サービス・マーク,トレード・ネーム,その他の営業の象徴となる標識,および経営のノウハウを用いて,同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え,一方,フランチャイジーは,その見返りとして一定の対価を支払い,事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。」というものであり,中小小売商業振興法4条5項及び11条は,「連鎖化事業であつて,当該連鎖化事業に係る約款に,加盟者に特定の商標,商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し,加盟金,保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(略)を行う者は……あらかじめ……次の事項を記載した書面を交付し,その記載事項について説明をしなければならない。」と規定し,その記載事項として,加盟金,販売条件,経営指導に関する事項,使用させる商標その他の表示に関する事項等を掲げる。さらに,公正取引委員会が昭和58年に作成した「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」は,「フランチャイズとは,定義によつてその範囲に広狭が生じるが,一般的には,特定の商標,商号又はそれらの一部,サービス・マーク等を使用させ,加盟者の物品販売,サービス提供その他の事業・経営について,統一的な方法で統制,指導,援助を行う事業形態であるとされている。……フランチャイズにおいては,本部と加盟者がいわゆるフランチャイズ契約を締結し,この契約に基づいて,本部と各加盟者があたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を呈して事業を行つているものが多く,両者の関係は通常の製造業者と販売業者のものよりも密接であるが,加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから,本部と加盟者間の取引関係は独占禁止法の適用を受けるものである。」と定義した上,「フランチャイズの取引関係の基本はフランチャイズ契約であり,同契約は,概ね次のような事項を含む統一的契約である。①本部が加盟者にその商号,商標等を使用し営業することの許諾に関するもの ②営業に対する第三者の統一的イメージを確保し,本部を含む加盟者の営業を維持するための加盟者の統制,指導等に関するもの ③上記に関連した対価の支払に関するもの ④フランチャイズの終了に関するもの」とフランチャイズ契約の一般的内容を示している。
そうすると,被告の主張するとおり,フランチャイズ契約においては,フランチャイザーが特定の商標やサービス・マークなど,統一的イメージを与える標識を使用させるとともに,事業経営のノウハウを供与してその展開を援助する内容が定められ,両者がいわばパッケージとされているのが通常と考えられる。したがって,一般的には,フランチャイザーとなるためには,上記のような標識について使用許諾する権限と事業経営のノウハウを保有することが必要と考えられる。
もっとも,このことは,フランチャイズ契約が常に上記のような典型的なものであることを意味するものではない。例えば,フランチャイザーは,一般的にノウハウの提供義務を負うことから,通常はそのノウハウの帰属者であることが多いと解されるが,提供義務を履行するためには,フランチャイザーが,時機に応じて,適時に,ノウハウを提供し得る態勢を有していれば足りるから,必ずしもノウハウの帰属者であることを要するものではない。同様に,フランチャイズ契約においては,フランチャイザーが常に1者(社)であることを要するものではない。資本や役員構成を共通にする複数の者(社)が,全体として対外的に統一的イメージを与えるグループ企業を構成している場合,これらが共同フランチャイザーとなって,フランチャイズ契約で定められた責務を分担することも十分にあり得るといわねばならない。すなわち,統一的イメージを与える標識の使用に関する権限を有する者と事業経営のノウハウの保有主体とが異なっている場合には,両者が共同フランチャイザーとなった上,前者が上記標識について使用許諾し,後者がノウハウの供与を行うことも,フランチャイズ契約の類型に含まれることは当然である。
(2)本件各フランチャイズ契約におけるフランチャイザーについて
ア 以上の観点に立って,本件各フランチャイズ契約におけるフランチャイザーの確定と,それが経営システムの保有主体の認定にどのように影響するかについて検討するに,前記前提事実に証拠(甲8の2ないし19,46,52,57の1ないし9,131,132,136の1ないし17,138,141,152,153,乙5の1ないし10,12,16,17,26,27,35,38,39)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(ア)一条工務店は,昭和53年9月12日に設立され,昭和61年2月28日,区分7(建築または構築専用材料,その他本類に属する商品)の指定商品について,「株式会社一条工務店」の商標登録を受けたのを皮切りに,平成11年1月29日までの間,多数の指定商品等について,同商標や「一条工務店」の商標登録を受け,その権利者となった。
原告は,昭和62年7月1日,一条グループにおける住宅関連業務の研究開発及びこれに関する経営指導等を目的として設立され,人的にも資本構成上も,一条工務店の子会社に位置づけられる。
なお,原告設立の前日である同年6月30日付けで,原告が経営システムの保有者及び供与者であり,一条工務店がその供与を受ける対価として,一定額のロイヤリティを支払う旨の昭和62年契約が締結されている。
(イ)原告設立以前に締結されたフランチャイズ契約書(契約番号1ないし9)においては,一条工務店とGCが契約当事者となり,一条工務店が上記商標権等の使用を許諾するとともに,経営システムの保有者及び供与者とされていた。
その後の住研時代である昭和63年中に締結されたそれら(契約番号10ないし12)においては,一条工務店,原告及びGCが契約当事者となり,一条工務店が上記商標権等の使用を許諾するとともに,原告が経営システムの保有者及び供与者とされていた。
また,平成元年から平成3年にかけてのそれら(契約番号13ないし18)においては,再び一条工務店とGCが契約当事者となり,一条工務店が上記商標権等の使用を許諾するとともに,経営システムの保有者及び供与者とされていた。
さらに,平成5年以降のそれら(契約番号19ないし21)においては,再び一条工務店,原告及びGCが契約当事者となり,一条工務店及び原告が区別されることなく,上記商標権等の使用を許諾するとともに,経営システムの保有者及び供与者とされていた。
(ウ)一条工務店は,原告設立後,それ以前にフランチャイズ契約を締結していたGC各社に対し,以後はロイヤリティを原告に支払うよう指示した。これを受けたGC各社の中には,その理由について疑問を感じた者もいたが,一条工務店と原告とはいずれも一条グループを構成し,親会社と子会社の関係にあることから,特段,支払先の変更に異議を述べることなく,原告に対してロイヤリティを支払うようになり,経理上の処理もそのように変更した。なお,その際,原告とGCとの間で,改めてフランチャイズ契約に関して契約書を作成したり,書面で承認を確認したりすることはなかった。
(エ)GC各社に対する研修は,一条工務店の管理センターにおいて,原告の従業員が講師となって行われ,その案内や各種マニュアル等の注文の受付けも,一条工務店の管理センターが行っていたが,モデルハウスの建築等についての設計や指導は,その現場等において,原告の従業員が行っていた。
もっとも,上記指導や研修等は,原告ではなく親会社である一条工務店の名義で実施されており,GC各社のうちかなりの者は,これらの実施主体が一条工務店であるとの認識を有していた。
(オ)また,GC各社に配布された各種マニュアル・カタログ類は,一条工務店ないし本部企画室等が作成者として表示されている。
このうち,「特注カタログ百年」,「特注カタログSAISON」,「間違いのない家づくり」,「あなたの土地を診断します」は,モデルハウス等を訪れた顧客に配布されるものであり,「設計事務所標準マニュアル書」,「安全施工基準書」,「大工工事施工マニュアル書’88」,「大工工事基本施工マニュアル書’91」,「設計マニュアル(H7.4.)」は,一条工務店ないしGC各社から外注先にも配布が予定されているものであり,「営業マニュアル(平成7年4月第2版)」は,一条工務店ないしGC各社の一般営業従業員に配布が予定されているものである。
(カ)原告の顧問会計事務所の田中範雄税理士は,原告の平成8年6月期決算が終了した平成8年8月ころ,経理担当者から,原告の利益率が大幅に減少したのは本件ノウハウ等を譲渡したからであるとの説明を受けたため,関係書類の整備状況について確認するよう指示した。
これを受けて,一条工務店業務推進室が改めて調査したところ,本件譲渡契約書と一条工務店及び原告の議事録の存在を確認したが,それだけでは十分でなく,原告とGC各社との間の契約書を整備する必要があると考え,平成8年11月7日のGCオーナー会議において,HRDの業務内容や本件譲渡契約の内容等を説明し,HRDとの間のフランチャイズ契約書,日付を遡らせた原告とGC各社間のフランチャイズ契約書,ノウハウの秘密保持に関する覚書に署名してもらうことを依頼し,平成8年12月19日付けで,GC各社に対し,上記各書類を同封して,署名の上返送するよう求めた。なお,その送付書には,冒頭に,一読後廃棄するよう求める記載があり,10周年記念賞与についての書面も同封されていた。
GC各社は,契約番号16の一条工務店鹿児島を除き,上記の要請に応じ,住研時代に日付を遡らせた原告との間のフランチャイズ契約に記名押印して,原告に返送している(なお,一条工務店鹿児島は,平成6年6月以降は,ロイヤリティの入金をしていない。)。
(キ)平成11年11月ころに行われた本件調査において,未来工務店(契約番号12)の代表取締役である山岡は,被告の担当者に対し,経営システムの提供は一条工務店から行われ,指導も浜松の一条工務店の管理センターで受けていたにもかかわらず,ロイヤリティを原告に支払っていたことについて疑問を感じていた旨述べており,クリヤマ(契約番号1)の元住宅産業事業準備室長である御牧元一も,経営システムのマニュアル類を契約締結と同時に一条工務店から受領し,その追加・改訂版も一条工務店から受け取り,指導等も一条工務店から受けていたと述べている。
他方,平成11年5月まで,株式会社一条工務店千葉(契約番号19)の代表取締役社長であった渡邉栄は,経営システムの供与者が原告に移行した経緯は覚えていないが,原告及びHRDも浜松の一条工務店という認識であり,両者を区別していないと述べ,さらに,株式会社木の国工房(旧一条工務店柏。契約番号14)の代表取締役社長である遠藤又四郎も,原告から経営システムの供与を受ける旨の契約を締結しつつも,一条工務店からその提供を受けるという考えでいた旨述べている。
なお,未来工務店は,平成10年に一条グループから脱退し,平成11年に至って,一条工務店の関連会社である株式会社日本産業から,総額1億5000万円を超える木材及び住宅設備機器等の売掛金請求の訴えを提起され(大阪地方裁判所平成11年(ワ)第11304号),平成12年11月21日,同年から平成21年までの10年間,毎年1000万円ずつ分割で支払う等の内容の和解が成立したが,平成14年7月5日,2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受け,山岡は所在不明となった。なお,クリヤマも一条グループから脱退している。
(ク)その後,原告は,GC各社(契約番号2ないし5,7ないし9,15,17)から,平成11年12月2日付け歴史的事実確認書と題する書面に代表者の記名押印をしてもらった上,返送を受けている。
同書面には,①原告設立に伴って,契約当事者を一条工務店から原告に変更したことについて口頭で了解をしたこと,②住研時代は,経営システムの提供は主として一条工務店が作成した連絡票,一条工務店の名前で開催する研修会等の手法で行ってきたが,その理由は,経営システムが原告という試験研究法人から供与されることが明らかになると,一般消費者にとって一条グループのイメージが悪くなり,また,GC各社も一条工務店研究開発部の名称で経営システムの供与を受ける方が事業経営上安心であることによること,③研修会の講師,モデルハウスの設計建築指導等を実際に行っていたのは原告の従業員である鈴木,平野,古沢らであることなどが記載されている。
イ 以上の事実によれば,本件各フランチャイズ契約書においては,すべて一条工務店が契約当事者として表示されているのに対し,原告については,一条工務店と並んで契約当事者になっているものも存在する(契約番号10ないし12,19ないし21)反面,原告設立前に一条工務店が当事者となって締結された契約が修正ないし変更されないままであったり(契約番号1ないし9),原告設立後に作成されたものですら,契約当事者とされていないものも相当数存在しており(契約番号13ないし18),また原告が契約当事者になっている契約書でも,一条工務店との役割分担が明記されているものとそうでないものとが存在するなど,契約書の作成,殊に当事者の表示について一貫した方針が取られておらず,企業の作成する文書として不自然であることは否定できない(この点について,原告は,原告を含めた三者間契約にすると契約関係が複雑になり,GCが一条グループを脱退した場合に,顧客との間に紛争が生じていると,迅速な引継ぎができない旨弁解するが,被告の主張するとおり,フランチャイズ契約と顧客の引継ぎとは別個の問題であるから,三者間契約にしたからといって不都合を生ずるとは考えられず,現に,三者間契約の方式に拠った契約が相当数存在することは上記認定のとおりである。)。
しかしながら,原告は一条工務店の子会社であり,対外的には一条工務店の会社名を前面に出した方が信用を得やすいと考えられることや,GC各社からみると,両社は同じ一条グループを構成し,これを峻別することによって格別の利益が得られるものではないと考えられること(両者の区別についてあいまいな供述をするGCが存在することは,これを裏付けるものである。むしろ一般論としては,親会社である一条工務店への信頼を背景として,本件各フランチャイズ契約を締結したと推測できるGCとしては,一条工務店がフランチャイザーとしてフランチャイズ契約上の全債務を負担する形式の方が安心できるとも考えられる。)を考慮すると,契約書に当事者ないし経営システムの保有者として原告が表示されていないからといって,直ちにその供与主体が原告ではなく一条工務店であると断定するのは相当でない。このことは,原告の従業員が,一条工務店の名義でもってGCに対する研修,指導に当たったことや,GC各社に配布された各種マニュアル・カタログ類の作成者が,一条工務店ないし本部企画室等と表示されていたことについても,同様と考えられる(殊に,カタログ及び資料は,住宅展示場を訪れる顧客に対して配布する営業上の資料であり,「設計事務所標準マニュアル書」,「安全施工基準書」,「大工工事施工マニュアル書」,「設計マニュアル」,「工務マニュアル書」は,一条工務店ないしGC各社の外注先にも配布が予定されたものであり,「営業マニュアル」は,一条工務店ないしGC各社の一般の営業従業員に配布が予定される営業方法に関するマニュアルであるから,一条工務店等の名義で作成されることについて合理的な理由があると考えられる。)。
かえって,GC各社が,一条工務店からの指示があったとはいえ,原告設立後は何らの異議を申し立てることもなくロイヤリティを原告に支払うようになり,経理上の処理もそのように変更した上,その多くが,日付を遡らせた原告とGC各社間のフランチャイズ契約書や歴史的事実確認書の作成の依頼に応じていることは,本件各フランチャイズ契約によって経営システムの供与主体が原告であること,すなわちフランチャイザーであると認識していたことをうかがわせるものである(原告がGC各社に対して歴史的事実確認書の作成を依頼することを決めた契機は,上記のとおり,税務調査が実施される可能性が高い旨顧問税理士から指摘されたことであるが,契約書の作成状況が不備である場合に,税務上の処理と整合させるべくこれを整備することは不自然なことではなく,まして,GC各社としては,その認識と異なる虚偽の契約書等の作成に応じなければならない理由はない。)。
(3)小括
以上を総合すれば,本件各フランチャイズ契約においては,契約書の作成方針に一貫性がなく,全契約を通じてフランチャイザーを統一的に確定することは困難であるものの,原告が経営システムの供与者,すなわち共同フランチャイザーである可能性を否定できない。
そうすると,本件各フランチャイズ契約における当事者の表示やノウハウ等の供与主体となるフランチャイザーの検討だけでは,経営システムの帰属主体がだれであるかを判定することはできないといわざるを得ない。
よって,その帰属主体がだれであるかについては,さらにその研究開発者がだれであるかなどを検討した上で,最終的に判断されるべきものである。
3 本件ノウハウ等の研究開発の主体について
(1)研究開発主体の判断要素
ある知的財産権の帰属主体を判断するに際して,最も重視すべき間接事実は,いうまでもなく,その研究開発の主体がだれであるかということである。したがって,本件においても,本件ノウハウ等の帰属主体を確定するには,その研究開発の主体がだれであったかを検討しなければならないと考えられるところ,それが一条工務店と原告のどちらであるかは,当該経営システムを研究・開発した人物がどちらに所属していたか(在籍状況),当該経営システムの研究・開発に必要な費用をどちらが負担していたか(費用負担状況)などの諸要素を重視すべきではあるが,それだけではなく,両社の営業内容,設立目的,設立経緯などからみて,どちらが保有するにふさわしいと考えられていたか(事業目的との整合性)をも総合的に検討した上,判断すべきものである。
そして,在籍状況,すなわち,当該従業者の使用者はだれかの判断においては,給与の実質的支給者はだれかという点が最大のメルクマールとなるが,それだけではなく,研究施設の提供,研究補助者の提供,指揮命令関係等を総合的に勘案して使用者を決定すべきものと解される。
もっとも,上記のような検討の結果,研究開発者の所属先や費用負担者が確定したとしても,被告の主張するとおり,事案によっては,これと異なる主体に研究開発の成果を帰属させる趣旨の合意が成立している可能性も否定できないが,このような合意が成立している場合は,通常,それを相当とする特段の事情が存在すると考えられるので,本件においても,かかる特段の事情が認められるかについても,併せて検討することにする。
(2)本件ノウハウ等の研究開発の状況
そこで,本件ノウハウ等の研究開発の状況について検討するに,前記認定事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア 原告及びHRD設立の経緯等(甲50,140,乙10)
(ア)一条工務店において採用されたフランチャイズ・システム
一条工務店は,前記のとおり,昭和53年9月12日に設立され,木造注文住宅の販売及び施工を営んできたが,昭和55年10月ころ,それに用いられる材木をあらかじめ可能な限り工場で加工し,これを現場で組み立てるという方法,すなわちプレ・カット工法を導入し,これによりコストを削減するとともに,非熟練の大工を有効に利用しつつ高品質を維持することが可能となった。
その結果,一条工務店の売上高が100億円に迫ったが,さらに事業を拡大するために,昭和61年ころから,各地の工務店とフランチャイズ契約を締結するようになった。その内容は,一条工務店が,GC各社に対し,商標等の使用許諾,木造注文住宅の販売・施工事業に関するノウハウ(経営システム)の提供及び指導,並びに各種住宅設備機器等の商品の販売を行い,他方,GC各社は,一条工務店に対し,経営システムの提供及び指導の対価として売上高の***ないし***のロイヤリティを支払うというものである。そして,一条工務店が提供する経営システムの内容は,契約書によれば次のとおりであるが,具体的には,木造注文住宅のモデルハウスの設計及び当該モデルハウスの施工に要する木材の加工方法(プレ・カット工法)が中心であった。
A 本品に関する材料の製造・製品の調達と品質管理
B 販売並びにマーケティングの要領及び管理
C 住宅に関する建築設計技術
D 住宅に関する建築工事技術
E 工事管理・監督の要領
F 本事業に必要な組織体制作り
G 本事業に必要な諸般の帳票・様式並びに管理手法
なお,フランチャイズ契約書には,一条工務店の商標権をGC各社が使用できる旨の記載があるが,フランチャイズ・システムを展開し始めたころは,一条工務店の商標が業界にそれほど知られておらず,GC各社の中には,フランチャイジーとなった後も,従前の商標を使用する会社もあった。
(イ)住宅展示場を中心とした営業
一条グループが営んでいる木造注文住宅の販売・施工事業は,住宅展示場に自社の営業従業員を配置した上,来場した顧客に自社の「商品」であるモデルハウスの魅力をアピールして注文を獲得し,受注後は,顧客の要望や敷地条件等に応じて,間取り・外観デザイン・内装デザイン・住宅設備機器を選択・決定し,実際に設計図書に従って木造住宅を施工するというものである。
したがって,一条グループの営業の成否は,住宅展示場の来場者に一条グループの商品の魅力を感じてもらえるか否かによって大きく左右されることから,住宅展示場が最も重要な営業活動の場であると認識されていた。
(ウ)原告の設立
昭和62年ころまでのGC各社は,プレ・カット工法に魅力を感じて一条グループに参加してきたが,同工法自体は,昭和30年代の終わりころから業界全体に普及し始め,昭和62年ころには,大手プレハブ住宅メーカーが,下請工務店を利用して住宅建築事業を展開しつつあった。
そこで,一条工務店は,プレ・カット工法だけでは売上増を見込めず,GC各社を一条グループにつなぎ止めておくことはできないと考え,①住宅販売業者にとって営業の中心となる住宅展示場に関するノウハウ(住宅展示場のモデルハウスの設計,飾り付け及び運営方法(営業方法))を提供すること,②建築技術についての学問的裏付けを行い,技術力をセールスポイントにできるような建築技術の基礎研究を行うこと,③多様な顧客ニーズに対応できる商品の多様化・オリジナル化を推進すること,これらの活動に特化した専門的部門を作るため,昭和62年7月1日,原告が設立された。
原告における研究開発及びGC各社に対する経営システムの提供は,一条工務店がそれまでに有していた経営システムを基礎としてなされることを前提としていたことから,その趣旨を明らかにすべく,同年6月30日付けで昭和62年契約の契約書が作成され,原告は,設立後,一条工務店からその経営システムを無償で引き継いだ。
イ 原告の従業員等の配置(甲67の1,67の2の1・2,67の3ないし24,67の25の1・2,67の26ないし37,67の38の1・2,67の39,140,154)
住研時代における原告の代表者は,一条工務店の代表者である大澄が兼務していた。
また,従業員数は,住研時代においては数十名であり,とりたてて組織系統図が作成されることはなかった。そのため,当初の従業員の配置状況を示すものは存在しないが,平成5年6月期ないし平成7年6月期における従業員の配置数は別表6のとおりであり,モデルハウス設計・商品開発部門に7人ないし8人,基礎研究・実験に2人(平野,古沢),原価管理に1人ないし2人,構造建方監修に1人ないし2人,平成6年7月期以降,地盤調査に3人,広報・連絡に7人ないし12人,木材加工に4人(平成5年6月期のみ)がそれぞれ配置されていた。これらの従業員に対しては,原告から給与が支給されていた。
もっとも,これらの従業員のうちの相当数の者は,一条工務店の部署にも席を有して,GC各社との対応に当たっており,一条工務店と原告の組織を厳密に区別することは困難であった。
ウ 原告による研究内容(甲67の1,67の2の1・2,67の3ないし24,67の25の1・2,67の26ないし37,67の38の1・2,67の39,68ないし81,82の1・2,83の1ないし3,84,85,86及び87の各1ないし3,88ないし95,96の1ないし3,97ないし99,139ないし151,154,乙39)
(ア)商品開発
原告は,鈴木を中心として,住宅展示場に建設されるモデルハウスの設計及び施工,インテリアコーディネイトの開発,新しいコンセプト・デザインの和風住宅ないし洋風住宅の開発,各種住宅設備機器の新商品の開発等を行った。そして,これら商品の開発に伴い,原告の住宅展示場設計担当者は,各地の住宅展示場に新たにモデルハウスを建築する際は,現地に赴いた上,そこに駐在しているGC各社のモデルハウス施工担当者や営業担当者らに対して,直接,モデルハウスの設計・施工指導,新しい商品知識の教育指導等を行っていた。このようにして,原告が,平成5年6月期から平成7年2月期の間,モデルハウスを施工した住宅展示場は,別表7のとおりである。
このような研究開発活動により,例えば,昭和63年ころに一条グループが売り出したタイル貼りの木造注文住宅は,大ヒット商品となった。もっとも,タイルの固定に用いられたセメントのあくが雨で染み出して外観を損ねるなどのクレームが出されたため,原告は,平成4年ころ,外壁のタイル貼りの工法を,従来の湿式から新乾式へと変更する内容の技術を開発した。この新しい施工方法の開発により,タイル貼り工法の大幅なコストダウンが実現されるとともに,外壁のタイルが立体感を持ち,全体としても高級感あふれる美しい外観を作ることが可能となった。また,原告は,昭和63年10月ころ,それまで禁止されていた木造3階建住宅の建築が解禁されたことを受けて,木造3階建住宅「ファミーユⅢ」モデルを開発した。さらに,原告は,顧客の生活スタイルの変化,生活水準の向上,求められる住宅設備機器の変化などに対応すべく,一条グループの主力商品である洋風住宅「SAISON(セゾン)」や和風住宅「百年」のモデルチェンジを行った。
その他の分野では,原告は,同年8月ころ,その販売・施工する木造注文住宅に,「住宅金融公庫高耐久性木造住宅仕様」を標準仕様として導入し,平成4年4月ころには,一条グループ独自の住宅設備機器として,システムクローゼットを開発した。また,原告は,平成5年ころ,「住宅金融公庫高耐久性木造住宅仕様」の普及のために,同制度の適用を受けるために必要な性能保証住宅登録機構への保証料を顧客に代わって一条グループが負担する制度や,全住宅を対象とした地盤調査に基づく住宅の20年保証制度などを創設した。さらに,原告は,上記システムクローゼット以外にも,キッチン背面の収納棚,ダイニング・カウンター収納棚,キッチン・カウンター,I型及びL型システムキッチン,シューズ・ボックス,洗面・脱衣ユニット,セカンド・キッチン,その他キッチン・アイテム,食器棚,収納棚,出窓等の新しい独自の住宅設備機器を多数開発している。
なお,原告は,平成2年9月に浜松,平成4年10月に名古屋,平成6年11月に福岡の各都市において,一条グループが提供する数々の住宅設備機器のショールームであるインテリア館の内装デザインを担当している。
(イ)基礎研究及び実験
原告は,昭和63年11月から平成7年2月の間,木造住宅に関する基礎研究活動を行うべく,従業員である平野及び古沢を中心に,東京大学大学院農学生命科学研究科等との産学協同による研究開発活動を実施したが,その内容は別表3のとおりである。
なお,平野及び古沢らは,一条工務店ないし一条工務店研究開発部所属従業員の肩書をもって,このような基礎研究及び実験を行っていた。
(ウ)地盤調査
地盤調査については,原告は,当初,GC各社から個別に相談を受けた案件について,基礎工事の方法を選定する方法で対処してきたが,従来の方法では既製コンクリート杭を地盤に打ち込む必要があるため,その過程でかなりの騒音や振動が発生し,数件ではあったが隣家の壁などにクラックが入ったなどのクレームがあったことから,振動等のない工法の採用が望まれた。
そこで,原告は,平成2年6月ころ,地盤改良方法としてDSP工法(地中に柱状の改良地盤を造成し,まさつ杭としての効果を発揮させる工法)を開発し,この問題を解決した。一条グループは,このような原告の地盤調査に関する研究開発活動を基に,平成5年ころ,住宅業界では初めて,受注したすべての施工現場を対象として地盤調査を実施することとし,これを受けて,従来は10年間であった住宅の保証期間を20年間に延長した。
(エ)原価管理等の指導
原告は,一条グループ全体の住宅資材の調達コストの低減を図るため,全国各地の業者の納入価格を調査・交渉し(主として仕様変更の際),GC各社に対して,より安いコストでの仕入れが可能となるような業者を紹介したり,様々な観点から原価管理について指導したり,個々のモデルハウス施工現場での営業方法についても指導するなどした。
エ 原告の研究開発費(甲100の1ないし3,152,153)
本件譲渡契約締結の前後における原告の決算報告書によれば,原告の売上総利益,販売費・一般管理費及び営業利益は,別表5記載のとおりである。なお,販売費・一般管理費の主要な部分は,人件費によって占められている。
そして,原告のロイヤリティ収入のうち,一条工務店から支払を受けた額は,平成6年6月期が約25億円,平成7年6月期が約33億円であり,これを一条工務店の営業期間に応じて分けると,平成6年3月から6月までのそれが税込み約6億7519万4797円,平成6年7月から平成7年2月までのそれが税込み約33億6459万2866円であるところ,この合計額は,一条工務店の平成7年2月期の開発研究費である39億9600万円とほぼ等しくなる(約6億7519万円と約33億6459万円を合計した約40億3978万円から消費税を控除した約39億2212万円)。
オ 各種マニュアル・カタログ類の作成名義(甲47,48,137,138,乙35,38,39)
一条グループが作成,配布する各種マニュアル・カタログ類については,前記のとおり,一条工務店ないし本部企画室等が作成者として表示されている。
もっとも,「特注カタログ百年」,「特注カタログSAISON」,「間違いのない家作り」,「あなたの土地を診断します」等のパンフレットは,モデルハウス等を訪れた顧客に配布されるものであり,「設計事務所標準マニュアル書」,「安全施工基準書」,「大工工事施工マニュアル書’88」,「大工工事基本施工マニュアル書’91」,「設計マニュアル(H7.4.)」は,一条工務店ないしGC各社から外注先にも配布が予定されているものであり,「営業マニュアル(平成7年4月第2版)」は,一条工務店ないしGC各社の一般営業従業員に配布が予定されているものである。
カ 本件特許権等の権利者(乙13の1ないし23,14の1ないし3)
一条工務店は,住研時代を含む平成元年1月27日から平成11年3月30日までの間,自己を出願人,平野(又は外1名ないし3名)を発明者又は考案者として,別表8のとおり,特許登録出願又は実用新案登録出願をしており,実際にも登録されてその権利者となっている。他方,原告が権利者として登録された権利は存在しない。
また,上記実用新案出願のうち,平成元年1月27日出願に係る考案については,考案者平野の住所として,一条工務店の所在地が記載されている。
(3)本件ノウハウ等の帰属についての総合的検討
ア 原告の設立目的,設立の経緯について
上記認定事実によれば,一条工務店は,プレ・カット工法などを武器に,順調な発展を遂げてきたが,昭和62年ころに至って,このままでは発展を維持できる保障がないとの認識から,競合他社との差別化を図るべく,一条グループの中で,建築技術や住宅設備機器等の研究開発及び住宅展示場を用いた経営方法の開発指導等に業務を特化した部門を設立することを決め,昭和62年7月1日,原告が設立されたことが明らかである。
このような原告の設立目的,設立の経緯に照らせば,一条グループの有する研究開発能力のすべてを原告に集中し,効率的な研究開発体制を築こうとするのが自然と考えられる(この一環として,それまでのノウハウ等が原告に帰属することを確認し,一条工務店がロイヤリティを支払う旨の昭和62年契約の契約書が作成されたものと考えられる。)から,原告設立後も依然として一条工務店が本件ノウハウ等の研究開発主体であったと認めることは困難である。
この点について,被告は,原告設立時において,それまで形成されていた一条工務店のノウハウが高額の収益をもたらすにもかかわらず,原告に無償でしかも口頭で譲渡されたと認めることはできない旨主張するところ,確かに,一条工務店は,原告設立前に,既に確立された経営システム等のノウハウをGC各社に供与するとのフランチャイズ契約を締結し,これによってロイヤリティを得ていたものである。
しかしながら,前記のとおり,一条工務店と原告とは,人的にも資本構成上も親子会社の関係にあるから,書面の作成(ノウハウの譲渡契約書ではなく,昭和62年契約の書面を作成するにとどまったこと)や譲渡対価の支払について格別の意を払わなかったからといって,特に不自然とはいえない上,上記フランチャイズ契約においては,経営システムについての守秘義務が規定されず,新たなノウハウの開発義務が明記されていたことに照らすと,一条工務店とGC各社とは,いったん経営システムが提供されれば短期間にその陳腐化が進行すると認識していたことがうかがわれるから,木造注文住宅建築に関する一条グループの研究開発機能を原告に集中させたとの上記の判断を覆すことはできない。
イ 本件ノウハウ等を研究開発した者の在籍状況について
上記認定事実によれば,モデルハウスの設計及び施工,インテリアコーディネイトの開発等は,原告の従業員である鈴木を中心として行われ,かつその基礎となる研究・実験は,同じく原告の従業員である平野や古沢らが,東京大学大学院農学生命科学研究科等との産学協同態勢などを通じて行っていたことが明らかであり,これによれば,本件ノウハウ等を生み出すに至った研究開発行為が,原告に在籍する従業員らによって行われたと認めることができる。
この点について,被告は,①研究開発者である大澄は,原告の役員であるとともに一条工務店の代表者でもあり,その活動を外形的に峻別することはできないこと,②平野,古沢らについても,一条工務店の従業員の肩書で成果となる各種開発技術の対外的な発表をしており,施主に対しても一条工務店の従業員として対応しており,また,一条工務店の管理センターが勤務地となっていることなどから,原告に在籍していた者についても,一条工務店による管理支配が行われている旨主張する。
しかしながら,①大澄については,被告もその活動がどちらの者のために行われたのか外形的に峻別できないと主張するにとどまり,大澄が原告のために研究開発したことを否定する証拠は存在しないこと(かえって,前記のとおり,一条グループの研究開発部門として原告が設立されたことに照らせば,その研究開発に向けられた活動は,原告のために行われたと推認される。),②平野及び古沢については,確かに,両名の研究発表は,一条工務店ないしは一条工務店研究開発部等所属従業員の肩書でなされ,施主に対する応対も一条工務店の従業員としてなされ,その勤務地も一条工務店の管理センターとされているものの,もともと一条工務店と原告とは,人的にも資本構成上も親子会社の関係にあり,GC各社を含めた外部に対しては,一条工務店の名称を前面に出して活動する方が,一条グループ全体の営業上も得策と考えられたことは推測に難くないこと,かえって,同人らは,原告から給与の支払を受け,原告の本来の業務とされていた建築技術の基礎研究を担当していたことなどに照らせば,被告の主張する「一条工務店による管理支配」の意味内容が明確でないことはさておいても,同人らの研究開発行為が原告のためではなく一条工務店のために行われたと認めることは相当でない。
ウ 開発研究費の負担について
原告は,上記認定事実のとおり,相当数の従業員を木造建築技術の研究開発や建築関連機器の新商品の開発に従事させており,実際にも多くの成果を上げ,一条グループの営業に貢献をしてきたものである。しかして,原告が上記従業員らに対して支給した給与の総額は,毎営業期においてかなりの金額に上っているところ,これらは,広義では研究開発費の性質を有すると解されるから,本件ノウハウ等の開発研究費は,主として原告によって負担されていたと認められる。
この点についても,被告は,①本件譲渡契約締結直前の平成7年2月期における一条工務店の研究開発費が39億9600万円余であるのに対し,同期に対応する原告のロイヤリティ収入は約31億円であり,このうち約10億円は,GC各社からのロイヤリティ収入であることからすると,差引約19億円(39億9600万円-(約31億円-約10億円))の金額は,一条工務店が自ら投下した研究開発費と評価することができること,②原告の事業内容には,住宅設備機器(商品)の輸入販売(いわゆる卸売販売)があり,この業務がかなりのウエイトを占めており,こうした業務には,多くの販売管理費及び人件費がかかるから,原告における人件費がすべて研究開発費に当たるとはいえないこと,③仮に,原告における人件費がすべて研究開発費であるとしても,ロイヤリティ収入に対する研究開発費は,極めて低額であること,④GC各社からのロイヤリティの支払は,GC各社と原告とのフランチャイズ契約に基づくものではなく,一条工務店の一方的な指示に基づいて行われていたことなどに照らせば,結局,同契約締結前の原告の収益の多くは,一条工務店から原告に投入された資金であるということができることなどを理由に,研究開発費用を主に負担したのは,一条工務店である旨主張する。
しかしながら,以下のとおり,被告の主張はいずれも採用できない。まず,①については,上記認定事実のとおり,原告の決算報告書及び総勘定元帳によれば,本件譲渡契約締結直前ころに原告が一条工務店から支払を受けたロイヤリティの金額は,一条工務店の研究開発費とほぼ等しいから,一条工務店は,原告にロイヤリティを支払い,原告からその開発した本件ノウハウ等の使用許諾を受ける以外,独自に多額の研究開発費を投ずることはなかったと認められる。
次に,②,③については,確かに,原告は,基礎的な建築技術や経営システムの開発と並んで,住宅設備機器等の調達・販売も行っているから,人件費のすべてが研究開発費の実質を有するものとはいえない(もっとも,被告は,住宅設備機器等の調達・販売に要する経費や業務が原告の業務のどの程度の割合を占めるかについて,何ら具体的に主張立証していない。)が,上記認定事実のとおり,相当数の従業員や施設を研究開発活動に投入し,かなりの成果を上げていることからすれば,人件費の相当割合がそのための経費としての性質を有することは否定し難いし,原告のロイヤリティ収入に比して,原告における研究開発費の割合又は額が少ないとしても,それが研究開発費としてのある程度のまとまった額を下回るような場合でない限り,原告が本件ノウハウ等の研究開発費用の主たる負担者であるとの認定を妨げるものではない。
さらに,④については,なるほど,原告設立時において,一条工務店からGC各社に対し,今後はロイヤリティを原告に支払うよう指示があったことが認められるが,だからといって,一条工務店が原告の行った研究開発活動の経費を負担していたと評価できるものでないことは明らかである(GC各社の中には,一条工務店と原告とを明確に区別していない者が存在していたことは前記のとおりであるものの,そのロイヤリティが,原告の開発した本件ノウハウ等の使用許諾の対価たる性質を失うものではない。)。
エ 本件特許権等の帰属について
上記認定事実のとおり,一条工務店は,住研時代に,自己を出願人,平野(又は外1名ないし3名)を発明者又は考案者として,多数の特許登録出願又は実用新案登録出願を行い,実際にも登録されてその権利者となっているところ,被告は,仮にこれらの発明・考案が原告の従業員によって開発されたものであるとしても,少なくとも,本件特許権等については,開発体制いかんにかかわらず,これを一条工務店に帰属させるとの合意が成立していたというべきであるから,これと関連する本件ノウハウ等も同様の扱いがされていたというべきである旨主張し,これを裏付けるものとして,昭和62年契約において,①対価の構成要素の一つとして「開発費」が明示されていること,②本件各フランチャイズ契約におけるロイヤリティ条項と異なり,契約終了後の守秘義務の定めや,マニュアル類の返還といった定めがないことから,ここにいうロイヤリティの実態は,原告の開発費用の負担及び知的財産権承継の対価としての意味を有するものというべきであると指摘する。
確かに,原告の従業員による発明・考案であるならば,本来は原告の名義で登録出願するのが自然と考えられるが,再三述べてきたとおり,一条工務店と原告とは親子会社の関係にあり,その営業政策上も,対外的には一条工務店の名義を前面に出すのが有利と考えたと推測できるから,本件特許権等が一条工務店に帰属するとの扱いを受けていたとしても,本件ノウハウも同様であるとはいえない(特許権等は公開されて外部の者の目に触れるのに対し,ノウハウは公開されない点に価値がある。)。
また,昭和62年契約(甲8の1,乙7)には,「乙(一条工務店)は甲(原告)から供与された「新しいノウハウ」と,これに必要な開発費とこれに伴う甲の教育指導に対し,その対価として次のロイヤリティを支払う。」と記載されているのに対し,他の本件各フランチャイズ契約については,「甲(GC各社)は,乙から許諾された販売実施権及び経営システムとこれに伴う乙の教育指導に対し,その対価として次のロイヤリティを支払う。」と記載されているが,ロイヤリティは,一般にノウハウの使用の対価であると理解されていること,いずれも,GC各社及び一条工務店が支払うのはロイヤリティであるとされ,その計算方法,支払方法,ロイヤリティ率もほぼ同様であること,昭和62年契約の「その対価として次のロイヤリティを……支払う。」の「その」は,文言上,原告から供与される「新しいノウハウ」であると解されること,仮にロイヤリティが何らかのノウハウの譲渡対価の趣旨であれば,そのことをうかがわせる文言があって然るべきであるが,そのような文言は存在しないことに照らすと,上記記載は,ロイヤリティ受取りの経済的動機の一つがその開発費の回収にあるという当然のことを意味するにとどまると解するのが相当であること,一条グループにおける経営システムに関して守秘義務条項が定められるようになったのは,平成元年に締結されたフランチャイズ契約以降であって,昭和63年までに締結されたほかのフランチャイズ契約においても経営システムに関して守秘義務の定めはないこと,これらによれば,「これに必要な開発費」は,単に動機を記載したものにすぎないと解されるから,昭和62年契約が,一条工務店が原告に対してロイヤリティを支払うことによって,開発された経営システムを譲渡する内容のものであるとの被告の主張は採用できない。
(4)本件先行処分等との整合性について
原告は,①被告ほかの課税庁は,過去において多数回にわたる税務調査を実施し,原告に本件ノウハウ等が帰属することを確認してきた,②被告は,平成9年7月4日,本件譲渡契約によってHRDが取得する本件ノウハウ等の対価とされた20億円が過少にすぎるとして,その適正評価額を31億2601万2066円と認定し,これを前提とする本件先行処分をしたものであって,その過程で本件ノウハウ等の内容について詳細に検討したはずであるから,本件各処分は根拠のない課税であるなどと主張するところ,本件先行処分は本件ノウハウ等が原告に帰属していたことを前提とするのに対し,本件各処分はそれが一条工務店に帰属していたことを前提とするものであるから,両者間に矛盾があることは否定できない。
この点について,被告は,本件先行処分の際には,その実態(帰属)を十分に把握していなかったと弁解するところ,証拠(甲61ないし63,65)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告は,平成7年2月28日付けで,原告に対し,一条工務店やGCに対する売上(ロイヤリティ収入)計上漏れなどを理由として更正処分(ただし,一条工務店からの売上げが二重に計上されていたなどの理由で,結論としては減額更正)を行った。
イ 原告から本件ノウハウ等の適正価額算定の依頼を受けた公認会計士増井高一は,本件譲渡契約締結に先立つ平成7年2月15日,一条グループの完工高とロイヤリティ率を基準として,本件ノウハウ等の上記価額を19億円ないし20億円と鑑定評価した。
ウ 原告は,平成9年の本件先行処分に先立ち,被告(及び中村税務署)による税務調査を受け,その結果,顧問税理士田中範雄は,被告の担当者から,本件譲渡契約によって原告がHRDに譲渡したのは,本件ノウハウ等そのものだけでなく,フランチャイズ契約の相手方からロイヤリティの支払を受けるシステム全体をも含むとの指摘を受けた。
そこで,原告は,本件譲渡契約締結日から1年間に原告が取得するロイヤリティ収入に複利減価率を乗じて本件ノウハウ等の適正価額を算出することとし,第1案(一条工務店についてはロイヤリティ率***)として28億2395万0176円,第2案(前同***)として34億2807万3957円を被告に提案したところ,その中間値である31億2601万2066円で合意が成立し,これに基づいて,被告は本件先行処分をした。
以上の事実によれば,被告の担当者は,税務調査の結果,本件譲渡契約によってHRDに譲渡されたのは,本件ノウハウ等そのものだけでなく,フランチャイズ契約によってロイヤリティの支払を受けるシステムそのものであるとの問題意識を抱き,原告と協議した結果,本件先行処分を行うに至ったのであるから,その過程において,本件各フランチャイズ契約に係る契約書等を精査したはずである。そうだとすると,被告が本訴において主張する契約書上の問題点(原告が当事者として表示されていないものが多いことなど)も当然に認識したであろうことは想像に難くなく,これを出発点として,さらに本件ノウハウ等の帰属についても問題意識を深めるのが自然と解されるところ,これについての検討が行われた形跡はなく,単なる適正譲渡価額の点を巡る課税処分に終わったことは上記のとおりであり,その意味では,本件各処分に至った事情は,やや不可解であるとの印象を免れず,被告の上記弁解は,直ちに採用することはできない。
付言すれば,本件各処分によって原告が新たに納付すべきこととなった法人税額は,平成8年6月期の更正処分による減額を考慮すると,実質的には原告の納付した外国法人税額の否認によってもたらされたものであるところ,上記外国法人税は,被告による本件先行処分の結果,これと整合する金額に増額されているから,原告は,本件先行処分に従ったがために,今回の本件各処分によって,平成8年6月期の減額更正によっても埋められない,より大きな不利益を被ったことは否定できない。
(5)小括
以上の検討結果によれば,本件ノウハウ等の研究開発主体は原告であったものであり,かつその成果を一条工務店に帰属させる必要性はなかったと認められるから,その帰属主体も原告であったと判断するのが相当である。
4 経済的合理性の有無について
(1)証拠(甲9ないし15,16の1ないし15,17,18,19ないし23の各1・2,24ないし34,35・36の各1ないし3,37の1・2,38,39の1ないし4,40の1ないし3,41の1ないし5,42の1ないし3,43の1ないし4,44の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 一条グループでは,同業他社との競争が激化するにつれ,それとの差別化をもたらす優れたデザイン,機能,耐久性等を有する商品の研究開発の必要性が認識され,大澄と鈴木を中心として,その計画の具体化に着手した。その過程において,上記の目的を達成するためには,原材料の供給先に近く,国内の他社への情報漏れを防ぎやすい海外に拠点を設けるのが有利と考えられ,検討の結果,地理的に東南アジアの中心に位置し,政治情勢も安定しているシンガポールにHRDを設立することに決定した。
イ HRDは,シンガポールのUOBビル内に本店を置き,経理事務等を行っているほか,ジュロン地区内のIMMビルに置かれたデザインセンターにて,住宅関係の各種研究開発や内装事業を行っている。
また,*****に置かれたHRDのフィリピン支店でも,住宅関係の研究開発や各種実験を行っており,台湾駐在員事務所では,原材料の市場調査や新商品の開発,さらには日本国内から指導員の派遣を受けて,中国の下請工場に対する技術指導などを担当している。
ウ HRDは,事業を展開するために,相当数の日本人及び現地人を雇用しているほか,本件資金移動に係る金員,役務提供・技術開発費,現地指導費用,研修費等の多額の費用を支出している。
上記認定事実によれば,HRDは,一条グループがさらなる発展を期すため,その企業戦略の一環として海外に設置されることとなった住宅関連技術等の研究開発部門であり,少なくとも現時点において,それにふさわしい人的,物的施設等の実体を備え,かつ多額の費用を投じていることが明らかである。
そうすると,HRDは,かつての原告のように,一条グループにおける建築技術,住宅関連機器等の研究開発拠点たることを目的として設立されたのであるから,一条グループの有する研究開発能力のすべてが集中され,効率的な研究開発体制を築くことが期待されていたと認めるのが相当であり,したがって,本件譲渡契約は,経済的,経営的な観点からする合理性を有していたと判断するのが相当である。
(2)この点につき,被告は,①昭和62年契約に基づいて,一条工務店は,既に本件ノウハウ等を自由に利用し得る地位にあったこと,②HRD,一条工務店及び原告の3社は,いずれも密接な資金関係にあり,また,役員構成も共通するところが多いことなどの事情を総合的に考慮すれば,HRDが原告から本件ノウハウ等を取得し,これを一条工務店へ供与する必要はない旨主張する。
しかしながら,昭和62年契約は,あくまで,原告が一条工務店に対して経営システムを供与する義務を負担する旨定めているにとどまり,一条工務店に経営システムを自由に利用し得る地位を保障するものではなく,しかも,密接な人的・資本関係にあるからといって,そのような関係のある会社間の取引の効力を否定する根拠になるものではない。かえって,上記認定のとおり,研究機関の拠点を海外において,建築資材や建築設備等の情報を円滑に取得し,かつ,その情報の保護を図るためにHRDを設立し,HRDにそれまでに集積された本件ノウハウ等を譲渡することには,十分な経済的合理性・必要性があると認められ,しかも,被告が自認するように,本件譲渡契約を仮装する動機も必要性もないのであるから,本件譲渡契約には経済的合理性がないとの被告の上記主張は採用できない。
5 本件各処分の適否
以上の検討結果を総合すれば,本件譲渡契約が仮装であるとの被告の主張は採用できない。そうすると,本件譲渡契約に基づいてなされた本件資金移動が法人税法22条2項所定の無償による資産の譲受けに該当しないことは明らかであるので,その余について判断するまでもなく,本件各処分(ただし,更正処分については,平成9年6月期は確定申告に係る税額を超える部分,平成10年6月期及び平成11年6月期については,平成11年11月26日付け各更正処分に基づく納付すべき税額を超える部分)は違法といわざるを得ない。
6 結論
よって,原告の本訴各請求は,いずれも理由があるからこれらを認容することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。