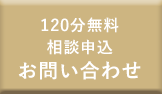高齢者に対して投資信託の商品説明をしてうなずいただけで申込書に署名させてよいか。
投資信託の販売では、顧客の知識・経験等に照らして説明をしなければなりません。ただうなずくだけでは商品の内容を十分に理解しているとはいえません。
したがって、説明方法に問題があるといえると考えられます。
【判例】
(1)平成10年法律第107号による改正前の証券取引法54条1項1号、2号及び証券会社の健全性の準則等に関する省令(昭和40年大蔵省令第60号)8条5号は、業務停止命令等の行政処分の前提要件としてではあるが、証券会社が、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとならないように業務を営まなければならないとの趣旨を規定し、もって適合性の原則を定める(現行法の43条1号参照)。また、平成4年法律第73号による改正前の証券取引法の施行されていた当時にあっては、適合性の原則を定める明文の規定はなかったものの、大蔵省証券局長通達や証券業協会の公正慣習規則等において、これと同趣旨の原則が要請されていたところである。これらは、直接には、公法上の業務規制、行政指導又は自主規制機関の定める自主規制という位置付けのものではあるが、証券会社の担当者が、顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為法上も違法となると解するのが相当である。
そして、証券会社の担当者によるオプションの売り取引の勧誘が適合性の原則から著しく逸脱していることを理由とする不法行為の成否に関し、顧客の適合性を判断するに当たっては、単にオプションの売り取引という取引類型における一般的抽象的なリスクのみを考慮するのではなく、当該オプションの基礎商品が何か、当該オプションは上場商品とされているかどうかなどの具体的な商品特性を踏まえて、これとの相関関係において、顧客の投資経験、証券取引の知識、投資意向、財産状態等の諸要素を総合的に考慮する必要があるというべきである。
(2)これを本件についてみるに、確かに、オプション取引は抽象的な権利の売買であって、現物取引の経験がある者であっても、その仕組みを理解することは必ずしも容易とはいえない上、とりわけオプションの売り取引は、利益がオプション価格の範囲に限定される一方、損失が無限大又はそれに近いものとなる可能性があるものであって、各種の証券取引の中でも極めてリスクの高い取引類型であることは否定できず、その取引適合性の程度も相当に高度なものが要求されると解される。しかしながら、本件で問題となっている日経平均株価オプション取引は、証券取引法2条22項に規定する有価証券オプション取引に当たるものであって、いわゆるデリバティブ取引の中でも、より専門性の高い有価証券店頭オプション取引などとは異なり、証券取引所の上場商品として、広く投資者が取引に参加することを予定するものである。
すなわち、日経平均株価オプション取引は、その上場に当たり、大蔵大臣の承認(平成9年法律第102号による改正前の証券取引法110条)を通じて、投資者保護等の観点からの商品性についての審査を経たものであり、また、基礎商品となる日経平均株価やオプション料の値動き等は、経済紙はもとより一般の日刊紙にも掲載され、一般投資家にも情報提供されているなど、投資者の保護のための一定の制度的保障と情報環境が整備されているところである。さらに、平成10年法律第107号による改正前の証券取引法47条の2(現行法の40条1項参照)は、有価証券オプション取引など、一般投資家の保護の観点から特に当該取引のリスクについて注意を喚起することが相当と考えられる類型の取引に関し、証券会社は、いわゆる機関投資家等を除く顧客に対し、契約締結前に損失の危険に関する事項等を記載した説明書をあらかじめ交付しなければならない旨を定めるが、この規定は、専門的な知識及び経験を有するとはいえない一般投資家であっても、有価証券オプション取引等の適合性がないものとして一律に取引市場から排除するのではなく、当該取引の危険性等について十分な説明を要請することで、自己責任を問い得る条件を付与して取引市場に参入させようとする考え方に基づくものと解される。そうすると、日経平均株価オプションの売り取引は、単にオプションの売り取引という類型としてみれば、一般的抽象的には高いリスクを伴うものであるが、そのことのみから、当然に一般投資家の適合性を否定すべきものであるとはいえないというべきである。
(3)日経平均株価オプション取引の以上のような商品特性を踏まえつつ、被上告人の側の投資経験、証券取引の知識、投資意向、財産状態等をみるに、原審の確定した前記の事実関係によれば、被上告人は、返済を要するものとはいえ、20億円以上の資金を有し、その相当部分を積極的に投資運用する方針を有していたこと、
このため、代表取締役社長自ら資金運用に関与するほか、資金運用を担当する専務取締役において資金運用業務を管理する態勢を備えていたこと、同専務取締役は、それ以前において資金運用又は証券取引の経験はなかったものの、昭和59年9月に本件取引に係る証券取引を開始してから、初めてオプション取引を行った平成元年8月までの5年間に、株式の現物取引、信用取引、国債先物取引、外貨建てワラント取引、株券先物取引等を、毎年数百億円規模で行い、証券取引に関する経験と知識を蓄積していたこと、オプション取引を行うようになってからも、1回目及び2回目のオプション取引では、専らコール・オプションの買い取引のみを、数量的にも限定的に行い、その結果としての利益の計上と損失の負担を実際に経験していること、こうした経験も踏まえ、平成3年2月に初めてオプションの売り取引(3回目のオプション取引)を始めたが、その際、オプション取引の損失が1000万円を超えたらこれをやめるという方針を自ら立て、実際、損失が1000万円を超えた平成4年4月には、自らの判断によりこれを終了させるなどして、自律的なリスク管理を行っていること、その後、平成4年12月に再び売り取引を中心とするオプション取引(4回目のオプション取引)を始めたが、大きな損失の原因となった期末にオプションを大量に売り建てるという手法は、決算対策を意図する被上告人の側の事情により行われたものであること等が明らかである。
これらの事情を総合すれば、被上告人が、およそオプションの売り取引を自己責任で行う適性を欠き、取引市場から排除されるべき者であったとはいえないというべきである。そうすると、Aの担当者(G及びH)において、被上告人にオプションの売り取引を勧誘して3回目及び4回目のオプション取引を行わせた行為が、適合性の原則から著しく逸脱するものであったということはできず、この点について上告人の不法行為責任を認めることはできない。これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきである。
5 以上によれば、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そこで、被上告人の主張するその余の責任原因について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官才口千晴の補足意見がある。
裁判官才口千晴の補足意見は、次のとおりである。
私は、法廷意見に賛成するものであるが、本件事案の特殊性にかんがみ、差戻審の審理について、次のとおり補足して意見を述べておくこととしたい。
オプション取引は、抽象的な権利の売買であって、その仕組みを理解することは容易ではなく、特にオプションの売り取引は、利益がオプション価格の範囲に限定される一方、損失が無限あるいは莫大になる危険性をはらむものであり、各種の証券取引の中で、最もリスクの高い取引の一つであるということができる。証券会社が顧客に対してこのようなオプションの売り取引を勧誘してこれを継続させるに当たっては、格別の配慮を要することは当然である。証券会社に求められる適合性の原則の要求水準も相当に高いものと解さなければならないが、本件においては、被上告人が一般投資家の通常行う程度の取引とは比較にならないほどの回数及び金額の証券取引を経験し、その経験に裏付けられた知識を蓄えていたことから、結論的に適合性の原則の違反は否定されるべきものである。しかしながら、本件取引の適合性が認められる被上告人についても、証券会社がオプションの売り取引を勧誘してこれを継続させるに当たっては格別の配慮が必要であるという基本的な原則が妥当することはいうまでもない。
このような観点から、本件においては、証券会社の指導助言義務について改めて検討する必要がある。すなわち、被上告人のような経験を積んだ投資家であっても、オプションの売り取引のリスクを的確にコントロールすることは困難であるから、これを勧誘して取引し、手数料を取得することを業とする証券会社は、顧客の取引内容が極端にオプションの売り取引に偏り、リスクをコントロールすることができなくなるおそれが認められる場合には、これを改善、是正させるため積極的な指導、助言を行うなどの信義則上の義務を負うものと解するのが相当であるからである。
本件においては、被上告人が主張する「顧客にできる限り損失を被らせることのないようにすべき義務違反」の趣旨は必ずしも明確でなく、この点についての主張、立証も尽くされているとはいえないが、本件の異常ともいうべきほどオプションの売り取引に偏った取引状況を見ると、Aがこのような義務を果たしていたといえるか疑問の余地があり、差戻審においては、このような点についても十分な検討がなされるべきである。
投資信託のようなリスク商品の販売については、適合性の原則に則った販売を行わなければなりません。適合性原則というのは、顧客の知識、経験や財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというものです(金融商品取引法40条1項)。
不適切な勧誘を行うことは相当ではありません。
適合性原則の判断基準としては、最判平成17年7月14日があります。これは、適合性原則に著しく逸脱した証券取引の勧誘の場合には不法行為が成立し、その際、顧客の適合性の判断については、具体的商品を踏まえ、顧客の証券取引の知識、投資経験、財産状態、投資意向の諸要素を判断することになります。
こうしたことから、本人の健康状態や会話の状況などからリスク商品の勧誘を行える状態にあるかを判断する必要があります。本件は,証券取引により巨額の損失を被ったXが,証券会社であるYに対し,Yの担当者によるオプション取引の勧誘行為は適合性の原則に違反するものであったなどと主張して,不法行為による損害賠償を求めた事案であり,その事実関係の概要は,次のとおりである。
2 本判決は,まず,証券取引における適合性原則違反と不法行為の成否に関し,証券会社の担当者が,顧客の意向と実情に反して,明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど,適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは,当該行為は不法行為法上も違法となるとの一般論を示したが,本件においては,Yの担当者による株価指数オプション取引の売り取引の勧誘が適合性原則から著しく逸脱するものであったとはいえないとして,不法行為の成立を否定し,原判決破棄差戻しとした。
3 証券取引法43条1項は,証券会社の業務の状況が「顧客の知識,経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており,又は欠けることとなるおそれがあること」のないように業務を営まなければならないと規定しており,この要請は「適合性の原則」と呼ばれる。この原則は,当初は通達(昭和49年大蔵省証券局長通達「投資者本位の営業姿勢の徹底について」等)及び日本証券業協会の公正慣習規則(規則9号「協会員の投資勧誘,顧客管理に関する規則」3条等)に根拠を有するものにすぎなかった。
しかし、平成4年法律第73号による証券取引法の改正により同法に取り入れられ(当時の54条1項1号),その後,平成10年法律第107号による改正により,証券会社の業務規制という位置付けで43条1号に規定されるに至ったものである。学説の多数は,適合性原則違反が社会通念上許容し得る範囲を超えるものである場合などには不法行為が成立すると解しています。
一般論自体は,下級審の裁判実務上も,ほとんど疑いのないものとして受け入れられているといってよいといえます。
有価証券オプション取引の勧誘に関して適合性原則違反が問題となった最近の下級審裁判例をみても,認容例は,社会経験の乏しい主婦を勧誘した事案(千葉地判平12.3.29判タ1094号187頁,判時1728号49頁)や,オプション取引の特質と危険性を認識させるような説明を欠いていた事案(京都地判平14.9.18判時1816号119頁)であり,個人投資家であっても,ある程度の証券取引の経験と財産的な裏付けを有する者に対して勧誘がされたという事例では,棄却例が多いようである(東京高判平14.10.17金判1174号2頁,さいたま地判平16.3.26金判1199号56頁,さいたま地判平16.6.25金判1199号10頁)。
本判決は,本件で取引の対象となった日経平均株価オプションの上記のような商品特性を踏まえつつ,Xの財産状況,投資意欲,投資経験等を総合して,結論として,適合性原則からの著しい逸脱があったとはいえないと判断したもといえます。
なお,才口裁判官の補足意見は,本件で適合性原則の違反は問えないとしても,証券会社の指導助言義務違反の有無という新しい観点からの検討が必要であると指摘するものであり,注目されるところである(証券会社の指導助言義務に関しては,潮見佳男「投資取引と民法理論(四・完)証券投資を中心として―」民商118巻3号362頁等参照)。