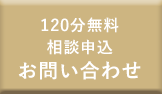事業者の賃借人と借地借家法
借主としては、事業所であれば営業の本拠を追われることになるものの、今般では賃借人の途中解約が有効か、という切り口も多く、対事業者という関係ではむしろ賃貸人の方が立場が弱いという事実認識も出てきている。
たしかに店舗として運営している場合は、退去に伴う有形無形の損害が大きく、おいそれと貸主の求めに応じられない、特に駅前などの好立地での集客型のビジネスなどはそうだろう。他方、事業者といっても、あまり立地が重視されない例えば建築設計事務所などは、退去に伴う有形無形の損害というのも、具体的に考えると電話番号が変わるかもしれない、という程度だ。
しかし、少なくとも裁判上は重大なことと位置づけられている。貸主が建物を返してもらたいというのは、一般的には健全な収益物件であれば、客観的に利益のはずであり、やむを得ない何かがあるというのが普通である。実際、やむを得ない何かといっても類型化することは可能であるが、特殊事情が介在していることが多い。少なくとも、第三者に貸して、適正賃料、適正契約という限度では、賃貸借は無個性とされその履行に何か特別なものがいるというわけでもないから、貸主側の言い分には、合理的なものと不合理性をはらむものがある。
一般的には、賃借建物の価値をはるかに超えた利害がからんでいるケースが多い。昔、成田空港の第2滑走路に未買収田畑があったため、飛行機が滑走路に近づいて迂回しなければならず、その間、飛行機の発着ができない、地上走行も出発機や到着機と衝突の危険があるなど、単に経済的価値だけに還元できないものがあるのもそうだろう。もっとも、この田畑もあっさり退去とならなかったように、借主側は、賃借建物の価値をはるかに超える利害がある場合はその分配を求め要求を強めることが一般的とすらいえる。しかし、所有者でもないのに、一種の支分権を分配しろ、という要求に貸主は納得いかないだろう。
このため、「カネさえ積めば」とはともかく、一般に対立は先鋭化しやすく、特に期間満了・正当事由に基づく明渡の場合は交渉による解決は困難で、訴訟になることもある。
そこで立ち退き料の提供と引き換えに和解というケースもある。しかし、訴訟の初期段階で和解に至るケースは少なく、双方尋問や不動産鑑定を経てようやく和解に至るということもある。
弁護士に依頼する際も、インテーク意見(初回相談による見立て)をつけにくい点に問題がある。それは「正当事由」「信頼関係」といった概念は見通しを悪くしており、しかも一般常識的な見地と借地借家法の趣旨からする見地では、定義も異なってくるからである。したがって、その判断枠組みが確立していない。正当事由に関してはいえば個々の裁判官で判断も異なり、過去の裁判例から結論を見立てられるほどではない。
また、正当事由を補完する立退料も算定根拠があいまいである。営業権もなかなか認めない裁判例であるから、テナントを変えれば営業可能な場合に、事実上引越し代という程度になることもあると思うし、テナント側もいつまでもそこにいるつもりで、借りていたという意識はないことが多いのも事実だ。この点、立退料は、正当事由を補完する要素であるので、自己使用の必要性が上回らないと検討にもあげられない、という裁判例もある。しかし、現実に使っている側と使っていない側で、使っていない貸主が自己使用の必要性を上回る場合などあるのだろうか、という疑問もあり、立退料の法的位置づけ自体に混乱がみられる。
特に事業物件の場合に、新規物件を探すのに必要な費用や一般的内装費を負担すれば、それは立退料になるのではないか、とも思える。
本件では、少なくとも正当事由の9割は具備されており、残り1割を借家権価格を立退料として支払うと主張する例もある。しかし、単なる賃貸借契約の場合は、借地借家法上の土地の賃貸借のように地震売買が行われるわけでもなく、移転の容易性というのも考慮されるのが相当のようにも思われる。
また、信頼関係は、いってみれば絆、主観的なものというのが社会の常識に合致しているが、裁判所的には、かなり寛容で主観的に信頼関係がゼロでも客観的に信頼関係ありとされるケースもある。
賃料不払いは最高裁の判決もあり、見通しはききやすいのだが、賃料不払い以外の契約違反の場合、信頼関係破壊のケースは、ケースバイケースで見立てるのは難しい。無断転貸、無断増改築、目的外使用の事例などがあるが、それも違反の内容はたくさんあり、類型化も難しい。
借主が店舗として利用している建物の明渡しを求める事例の場合、借主の自己使用の必要性に関し、当該店舗の収益状況が問題となる。過去の裁判例でも、移転に伴う休業期間分の損失や移転後の減益を考慮した営業権補償を加味するという例はある。こうした場合の売上の減少そのものが逸失利益になる場合もあるが、粗利率がとれくらいなどか、つまりは売上総利益ということになるが、また販売管理費はどれくらいあるのか、営業利益はどれくらいなのか、経費のうち休業によって支出を免れる変動費、免れない固定費といった反論にあたり検討すべき点もある。一見すると税引き前利益で計算しているケースでも、損益計算書をみてみると、株式譲渡で得た利益(特別利益)あるいは営業外収益によって利益が出ているにすぎず、営業利益がマイナスということもある。そこで、店舗の移転・休業によって左右されるのは営業利益であり、営業とは無関係の営業外収益は営業補償の範疇を超える。営業補償が高額になると予想される事案では、税理士・公認会計士の協力も必要になると思われる。