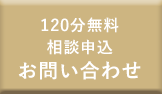法科大学院、一度足をとめてみては?
3日付読売新聞が、法科大学院についての社説を掲載した。
読売は「有能な人材の法曹離れを食い止めるためには、養成制度を大幅に見直すしかあるまい」と指摘しているが、法曹産業というのは1兆円市場である。医療産業は100兆円産業ともいわれるが、産業別に抱えきれる労働者や事業者の数は限定される。法曹に有能な人材を集めたいということであれば、情緒的に「敷居が高い」とか、「(無理筋であることを看過して)依頼を受けてくれる弁護士がいない」といった主観的不満を乗り越えて、理性的な数に限定していく必要はある。
また、弁護士といっても、隣接業種として公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士がおり、これらも1兆円産業内におけるプレーヤーである。したがって、まずは合格者の数を限定する必要があること、絶対評価を高めること、サンクコストを少なくすること―などが挙げられる。
弁護士の偏在などの論拠も、いわゆるゼロワン地域がなくなったことやそれら地域の弁護士事務所の経営が厳しいことに照らして、現実的ではないことが明らかになったといえる。
法科大学院制度を見直しても、根本的には「学校利権」の問題に還元されてしまう可能性もある。今後は予備試験など地方でも司法試験を受験できる内容にするのが相当だ。
法科大学院の改革では、「法曹コース」の創設なのだという。しかし、一部私大では、5年生は既に行われていたことであり、今更の案がこんな内容のものというのはいささか暗澹たる気持ちになる。また、いまや就職は「売り手市場」だ。こうした景気の中で法曹の志望者が減少するのは、自然なことであり、無理に法曹になりたくない者になってもらう必要まではないだろう。
そのうえで、勉強時間を減らして学生を確保する狙いがあるとすれば法科大学院制度からして、本末転倒の感を否めない。
そもそも、司法制度改革の理念自体が間違っていたといわざるを得ない。弁護士はいま無料相談も多くしているが、プロフェッションに診察や相談するのに、普通無料などあり得ないのだ。そうした間違った社会通念の確立や法テラスを通じた弁護士費用の切り下げ圧力が弁護士の職業としての経済的基盤を揺るがし、ひいては、弁護士としての使命感や職業としての魅力の減少につながっているのではないか。
弁護士は国民にとって身近ではない。それは、法律行為自体が国民にとって身近ではないからだ。それを無理やりトラブルを起こすような「身近な司法の実現」というのは、私たちが目指す社会的正義とは異なるように思われる。
また、いわれた法曹ニーズは、弁護士の経済的基盤も考えず、企業から「安く使える都合の良い鉄砲玉」弁護士を求めるというニーズを、「適切な法曹ニーズ」とはき違えた点が大きく、「飛躍的な拡大」などというのは見込まれる余地はなかった。
法曹ニーズを論じるには、司法需要がどれくらいあって、ひとりあたりの割り当てが平均どれくらいになるのか、根拠のある数字とエビデンスを示した議論が必要だ。なにやら「飛躍的に増大するつもりが思うように増えず」では根拠があいまいで砂上楼閣であったことを示す。
法科大学院の志願者減は深刻というよりも、法科大学院の「利権」を中心とする議論にはうんざりする。かつては74校が、まさに「乱立」であったように、あるべき法曹像を起点に数字とエビデンスで討議をするべきである。
この点、読売は、学校利権を擁護する立場から「行き詰まりの最大の要因は、司法試験での合格率の低迷」というが、絶対評価であれば、それは法科大学院側に問題があるのだといわざるを得ないだろう。
「学生の目標は司法試験に合格し、法律家として社会のために貢献することだ」だが、それに対する手段が、「各校のカリキュラムも再構築」のような小手先のものに終始してしまうことも残念だ。